公式インタビュー 日本映画・ある視点 『ひとつの歌』
杉田協士監督

映画は実人生とは別物だと考えている人は多く、また大半の人はそうであってほしいと願っている。そういう人たちにとって、映画は日常生活から逃避する手段だから、現実との共通点が少なければ少ないほどいい。杉田協士監督は、この信条を必ずしも否定しているわけではないが、彼の創作アプローチはほぼ正反対である。杉田監督の長編デビュー作品『ひとつの歌』におけるユニークな話法についての説明として、彼はストーリーやビジュアルよりも、時間を扱うことへの関心が強かったと語り、映画のワンシーンを例にあげて解説してくれた。
「夜の駅のホームのシーンで、ヒロインの桐子が剛に『私、行きたい場所があるの』と言ったときに、ふたりの距離は縮まらないけれど、そこの空気が震えて、今までと違う時間が流れるのです」
そこに電車が来て、シーンが変わり、さらに時間軸が変化していく。杉田監督が言わんとすることはおそらく、各シーンには独特の時間感覚や空気があり、できる限り正確にその感覚を伝えたいということだろう。問題はさまざまな出来事が観客の知らないうちにシーンとシーンの間で起きていること。そのため、実際に観客が観て、聴いて、感じることと筋を通すために、登場人物たちの言動そして画面に映るあらゆることが、観客が直接的には体験しない物語の詳細を補完している。
『ひとつの歌』にはかなり古典的な筋書きがあるが、その中心的な出来事の多くは示されない。それは実人生では物語の元になる出来事をすべて経験するのは不可能だからだ。主人公の剛(金子岳憲)は寡黙で内向的な若者で、他人のポラロイド写真をなるべく被写体に気付かれないように撮るという、趣味―あるいは執念とも見える―をもっている。ある日、駅のホームで彼は読書している女性を撮影するが、その後、彼女は死んでしまう。剛は死んだ女性の娘、桐子(石坂友里)と知り合うことになるが、彼女には彼が死ぬ直前の母親を見たことは伝えていない。要約するとそういう筋書きだが、少なくとも二度は観ないと大半の情報を読み取れない観客も多いかもしれない。物語の最もドラマチックな部分の間に起こったことのみが描かれているからだ。
その結果、作品はランダムに脱線していくように見える。あるシーンで、剛がピンク色のTシャツを着た男のあとを追い、家に入ろうとするところを写真に撮るが、男はそのことに気付いていたようだ。実際、このシーンが物語の中核である。杉田監督いわく、
「剛はピンクTシャツの男に何かしらの共通点を感じ取ったのです。そして先の女性が亡くなる原因となった事故は目撃していませんが、あれは事故ではなく、ピンクTシャツの男が関わった事件ではないかと疑って、あとを尾けたのです」
登場人物のひとりは自殺を図り亡くなるが、手がかりはほとんど存在しないくらいに極めて微妙で、たいていの観客は気がつかない。
「これまでに、20人にひとりくらいは気が付きました」と杉田監督は話す。

映画監督は作品世界のすべてを操ることからしばしば神と比べられるが、杉田監督は脚本を書くにあたり、登場人物の人生の年譜を作ったと言う。
「でも役者には見せていません。実際の人生で人に会ったとき、その人の表面しか知りえないし、すべてを理解するのは不可能です。私は映画も現実のように描きたいと思い、登場人物たちも皆、謎めいた感じを残しました。」
ある意味、物語の中心部分の多くを削ぎ落とした彼の手法は、登場人物たちの“プライベートな時間”への配慮とも言える。言い換えれば、監督には関わりのない部分なのだ。
この作品の語り口は剛の自信のなさも反映している。庭師という職業柄、彼は仕事のために他人と関わる必要がなく、依頼者が彼と仕事仲間にお茶を出し、雑談をしようとする場面でも、態度は丁寧だがほとんど口を開かない。あまり会話好きでない人がどのように他の手段を用いて感情を表現できるのかを示すことが杉田監督の目指すところでもある。
「うまくコミュニケーションできなくて黙っているけれど、何らかのメッセージを発信する人に、私はよく出会います」

剛にとって、写真はコミュニケーションの手段であり、だからこそポラロイドであることが重要なのである。
「剛は写真家ではないので、普通のフィルムを使うと、現像に出すときに店員と話さなくてはならなくなります。彼はそういう会話すらできないのです」
ポラロイドは、誰にも頼らずに望んで手に入れられる彼の欲求の物的証拠なのである。
しかし、映画のラストまで写真が1枚も映し出されず、またそのラストシーンでもたった1枚しか現れないのは不思議に感じる。
「写真にはすでにフレームがあります。そこにさらに映画のキャメラを使って別のフレームを重ねてしまうと、写真という物体にしかならないのです」
それが望ましくないのかどうかについては言及しなかったが、いずれにせよ、杉田監督はこの作品が劇場公開される際には剛が撮影したポラロイドの写真展を併催したいと話す。展示する写真には、その後の剛の生活も写したものも含める予定だそうだ。通常、観客はエンドマーク後の登場人物たちの暮らしについて考えることはないが、杉田監督は違う。ドラマチックな出来事の後も彼らの人生は続く。
「私はそういうことを考えていきたいのです」
聞き手:フィリップ・ブレイザー(映画ライター)
ひとつの歌
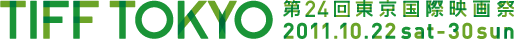

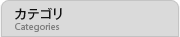

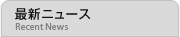




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
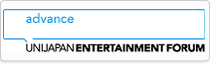

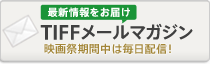
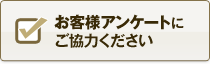

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)