公式インタビュー コンペティション 『トリシュナ』
マイケル・ウィンターボトム監督

インドを舞台に置けば、ハーディが描いたイギリスの状況が、もっとダイナミックに展開できると思った
マイケル・ウィンターボトム監督の『トリシュナ』は、文豪トマス・ハーディの代表作「テス」を、19世紀のイギリスから現代のインドに舞台を移して映画化した作品だ。インドの貧しい村で育ったトリシュナは、裕福なイギリス人ビジネスマンのジェイに出会い、恋に落ちる。だがそんなふたりは、急速な変貌を遂げる社会に飲み込まれていく。ハーディの精神を現代に甦らせたウィンターボトム監督に話をうかがった。
―――ハーディの作品の映画化は、『日陰のふたり』、『めぐり逢う大地』につづいて3度目になりますが、ハーディに惹かれるのは大学で英文学を学んだからなのでしょうか。『めぐり逢う大地』の場合は、アメリカがアメリカになる前の世界を題材にした作品の構想を練っているうちに、それがハーディの小説と結びつくことになったわけですが、『トリシュナ』の場合も現代インドが先にあって、それが「テス」に結びついたのでしょうか。
マイケル・ウィンターボトム(以下、ウィンターボトム監督):ハーディは大学に入る前、十代の頃に読んでいて、とても好きな作家だった。一番気に入っていたのが「日陰者ジュード」だったので、まず『日陰のふたり』を撮った。『トリシュナ』の場合は、確かにインドで仕事をしていたときに「テス」を思い浮かべたということもあるけど、『日陰のふたり』を作ったこととも関係している。「テス」と「日陰者ジュード」はハーディの最後の作品で、彼にとっての同時代の社会を批判するラディカルな小説になっている。
それで、『日陰のふたり』では、原作に忠実に19世紀のイギリスを舞台にした。それはそれで意味があったと思うけれど、ハーディが描きたかったラディカルな現代批判の部分は少し薄れてしまった。たとえば、蒸気機関車は当時では最新のテクノロジーだったけど、現代の視点に立つとノスタルジックに見えてしまう。ところが現代のインドであれば、ジェット機も携帯もラップトップもWi-Fiもありながら、村落社会では昔と変わらない農法が行われ、ハーディが描いたイギリスの状況がもっと極端なかたちで現れている。だからハーディの世界をダイナミックに展開できると思った。

――ハーディの「テス」では、テスのような女性を抑圧するキリスト教に対して、女性の魂のなかには遠い祖先の異教的な想像力とどめられているといった表現が見られますが、インドの場合はどうなのでしょう。
ウィンターボトム監督:インドでは肉体的で官能的なものが、宗教上は受け入れられているように見える。ところが実際の社会は非常に保守的で、結婚も含めて女性の役割が決められていて、それを越えてしまうといまだに受け入れられないところがある。ハーディの世界はもう少しシンプルで、彼は「テス」のなかでもはっきりキリスト教を批判している。動物が妊娠することは非常に自然なことで、テスが妊娠することもそれと同じなのに、教会が入ってきたがために問題になる。結婚して生まれた子供ではないので教会に認めてもらえない。キリスト教では官能性が拒絶され、女性が非常に抑圧されているという意味でシンプルだが、インドの場合は宗教上は受け入れられるように見えながら、実社会では受け入れられない。そういう非常に曖昧なところがあり、その矛盾も描きたかった。
――ジェイを演じているリズ・アーメッドは、監督の『グアンタナモ、僕達が見た真実』にも出演していますね。ジェイがトリシュナに対してとる支配的な態度と、ジェイという人物のバックグラウンドの関係についてはどのように考えていましたか。
ウィンターボトム監督:リズ・アーメッドにとっては、『グアンタナモ~』が初めての映画の仕事だった。オックスフォード大学を出たインテリで、MCやラップもやるという複雑で面白い人物だ。彼が演じるジェイは、裕福なイギリス人とインド人の間に生まれ、イギリスで育ち、友だちもみなイギリス人で、バックグラウンドはイギリスにある。トリシュナに対する態度は、生きる環境がまったく違うことも考えずに恋をし、境遇に同情することもない。そうした想像力の欠如が一番の原因になっている。
それから、この映画の背景のひとつにツーリズムやポスト・コロニアリズムというものがある。ジェイや彼の父親はホテルを経営することによって、日本やヨーロッパの観光客をマハラジャの邸宅だった建物に泊まらせたりして、植民地時代の経験をさせる。特にふたつ目のホテルに移ったときに、ジェイはのさばり、それこそマハラジャの王子のような態度をとるようになる。そういう意味ではネガティブなイメージがあるけど、一方で、ラジャスタンでは実際にホテルが一大産業になっている。それが特に女性に雇用機会をもたらしている。でもそこには矛盾もあり、トリシュナは本当に奴隷のようになっていき、彼女の同僚にはキャリアになっている。ラジャスタンは保守的なところだけど、私は実際にこの同僚のような女性たちにたくさん会った。観光業界で働いていて、非常に野心に満ちて自立していて、成功したいと思っている女性がいることも事実なのだ。
――この映画にはトリシュナのダンスとも結びつくかたちで様々な音楽が使われています。スーフィズムの音楽であるカッワーリーの第一人者だったヌスラット・ファテ・アリ・ハーンの曲も印象に残りました。どんな曲をどのように使うか、すべて監督が決められたのでしょうか。
ウィンターボトム監督:音楽はみんな自分で選んだ。この映画の音楽にはいろいろなレベルがある。まずインドでは、寺院、トラックやタクシー、民家など、どこでもスピーカーやテレビから音楽が流れてくる。音楽とダンスがインドというもののテクスチャーになっている。この映画ではボンベイの本物のダンサーたちを使っているけれど、彼女たちに話を聞くと、テレビのダンスシーンを真似ることからダンスを始める人が多いので、その音楽も使った。それから私が一番好きなのが、クレジットもされている梅林茂さんの曲。彼が愛のテーマを書いてくれて、トリシュナが恋に落ちていくシーンと関係がだめになっていくシーンで効果的に使っている。ボリウッドの作曲家も4曲提供してくれていて、その歌詞と映画のなかで起こっていることがパラレルになっている。
ヌスラットの音楽は、スピリチュアルで美しく、私も大好きだけれど、それと同時にインドの巷で実際によく流れているということもあって使っている。

――あなたは世界各地で映画を作っていますが、日本を舞台に作ってみたいと思うことはありますか。
ウィンターボトム監督:確かに東京が大好きだし、何度かきているので、できれば作りたいと思っているけどなかなか難しい。まず自分がイギリス人の監督なのでイギリス的な視点がほしい。『トリシュナ』に関していえば、イギリス人がインドに行って恋に落ちたということで、そこにイギリス人としての視点があった。ただ、私が作ってきた映画というのは、故郷を離れるとか、亡命するとか、新しい場所へ旅立つというものだったので、もしかしたらそのうち東京で撮るかもしれない。
※ ※ ※
ウィンターボトム監督が切望し、叶わなかった企画に、フランスの作家ミシェル・ウエルベックの小説『プラットフォーム』の映画化がある。父親を亡くした男と、若い旅行会社重役の女が南国タイで出会うこの小説では、性愛とツーリズムやポスト・コロニアリズムが結びつけられている。彼がこの小説も意識していたことは間違いないだろう。そういう意味では『トリシュナ』には、ハーディの精神とともに、最も現代的な視点が盛り込まれていることになる。
聞き手:大場正明(映画評論家)
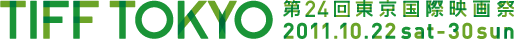

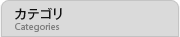

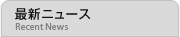




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
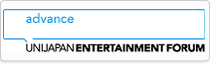

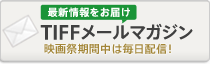
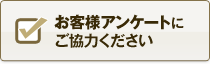

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)