公式インタビュー コンペティション 『ガザを飛ぶブタ』
シルヴァン・エスティバル監督、ミリアム・テカイア(女優)

マージナルな立場にこだわり、他者を理解し、受け入れる
『ガザを飛ぶブタ』では、紛争が続く世界に一匹の豚が放り込まれる。ガザに住むパレスチナ人の漁師ジャファールはある日、一匹の豚を釣り上げる。苦しい生活を送る彼は、その不浄な動物で金を儲けようと、入植地で豚を飼育するロシア系イスラエル人のエレーナに接触するが・・・。ユニークな発想とユーモアで、豚を架け橋にしてみせたシルヴァン・エスティバル監督と、エレーナを演じた女優ミリアム・テカイアさんにお話をうかがった。
――エスティバル監督にとってこの映画は初の長編になりますが、それ以前に様々なフィールドで仕事をされていますね。
シルヴァン・エスティバル監督(以下、エスティバル監督):パリで学生のときにジャーナリストの活動を始めました。アフリカ関係の雑誌で仕事をするようになり、サハラ砂漠とかに行って記事を書いていました。ボスニア紛争のときには、カメラマンとして現地で取材をしました。その後、AFP通信社に入り、本を書くようになり、小説も出し、短編映画を手がけるようになり、映画監督になりました。
――あなたが書かれた小説が、カリム・ドリディ監督、マリオン・コティヤール、ギョーム・カネ主演で2009年に『Le dernier vol』として映画化されていますが、その小説はどんな話だったのでしょう。
エスティバル監督:1933年にサハラ砂漠に墜落した飛行機を題材にしていて、事実とフィクションを混ぜ合わせた物語です。その飛行機は62年になってようやく発見されるのですが、操縦士が救助を待ちながら8日間にわたって記録をつけていました。私はその記録をもとに小説を書いたのですが、映画ではそういう部分がほとんど描かれていません。
――もともと映画を撮りたいと思っていたのでしょうか。それとも、別のキャリアを積み重ねるうちになにかきっかけがあったのでしょうか。
エスティバル監督:もともと写真や映画など、映像に惹かれていましたが、自分で映画が作れるとは思っていませんでした。短編を作ってみて自信がついたのと、いま質問をされた『Le dernier vol』を観て、これだったら私にもできる、自分で監督したほうがいいと思って、監督になりました(笑)。

――映画を観ていて、イスラエルでは爆弾テロを避けるために豚を飼育しているという記事を昔どこかで読んだことを思い出しました。そこで、豚を登場させることで、こういう映画が作れるのかと、うなったのですが、どういうところからインスピレーションを得たのでしょうか。
エスティバル監督:実は、私もそういう話を聞いたことがありました。私はウルグアイに住んでいるのですが、ウルグアイではイスラム教の犠牲祭のために、たくさんの羊が船で運ばれていきます。その光景を目にして、それが羊ではなく豚だったらと想像して、イスラエルで実際に豚が飼育されているという話と結びつきました。海から豚がやって来て、その豚がイスラエルとパレスチナの架け橋になったら面白いと思いました。
――テカイアさんはチュニジア出身とのことですが、最初から女優を目指されていたのでしょうか。
ミリアム・テカイア:もともと音楽方面に進もうとしていたのですが、発声とか発音を矯正しようと思って、10日間の演劇コースに通って、コーチングを受けているうちに、芝居がすっかり好きになって方向を変えました。女優になることは仕事というよりは、人生の使命のように感じています。音楽はすごく好きで、最高の芸術だとは思っているのですが、自分自身が性格上、人前に出ることを苦手にしていました。演劇をやりだしてから、それを変えました。映画学校にも4年通って、その間にいろいろオーディションも受けました。フランス人が登場する台湾映画があって、大きな役というと、その作品とこの映画ですね。

――監督はこの映画の現実的な部分についてはいろいろリサーチをされたのでしょうか。
エスティバル監督:以前にAFP通信社の仕事で、1年かけてガザ地区のルポルタージュを作ったことがあります。10メートルくらいしか離れていないところに暮らす、パレスチナ人の家族とユダヤ人の入植者の家族にカメラを渡して日常を写真に収めてもらい、1年後に交換してみるという企画です。
そのおかげで双方の日常をよく知ることができました。ただ、この映画は、現実を見ながらも、想像の世界を広げていくものなので、本当のガザを見たという気持ちになられては困ります。現実とともにコミカルな世界を見てほしい。
――ジャーナリストでもある監督のなかから、豚のピンナップとか、兵士がリューマチの特効薬と思って豚の精子を飲んでしまうようなユーモアが出てくるところに、意外性も感じるのですが。
エスティバル監督:あれはAFPから出てきたものではありませんよ(笑)。私の想像力から生まれたものですが、怒りをそのままではなく、コミカルに表現しているという側面もあります。ちょっと趣味の悪いユーモアを使うことで、耐え難い現実を変えていく試みであり、抵抗がユーモアとして表れています。チャップリンがインスピレーションの源になっていて、イタリアのエットーレ・スコラのユーモアもヒントになっています。
――テカイアさんは、この映画の企画と自分が演じるキャラクターに最初はどのような印象を持たれたのでしょうか。
ミリアム・テカイア:彼とはパートナーなので、シナリオを書いていることは知っていました。ある日、彼から電話がかかってきて、すごくいいアイデアを思いついたから、この役をやってほしいといわれました。ちょうど他の映画に関わっているときで、豚を育てる役だと聞いて、自分にできるのかとも思いました。
エスティバル監督:この映画で、ミリアムが演じたエレーナと、漁師のジャファールというのは、どちらも社会から外れたマージナルな存在なのです。そこで繋がりができていくわけですが、ミリアムもコミュニティから離れているという意味で性格がとても似ていると思いました。彼女はこの役を頼まれてとても驚いたようですが、私はすごく理にかなっていると思っています。最終的にはユダヤ人であるかないかではなく、性格が似ていたから合っているのだと思います。

――漁師をイスラエル人のサッソン・ガーベイが演じ、エレーナをチュニジア出身のテカイアさんが演じるというのは、最初から考えていたことなのでしょうか。
エスティバル監督:主人公の男性を誰にしようか考えていて、『迷子の警察音楽隊』の主人公を演じているサッソン・ガーベイがいいということになりました。あとから彼がイスラエル人だと知って、これは面白いと思いました。紋切り型のものを壊して、映画の意味が両方向に向かうのではないかと。ただ、最初はそういうバックグラウンドは消し去って、物語に集中して観てほしいと思います。サッソンは一種の鏡のような存在です。何も知らずに観れば彼は本当にパレスチナ人だと思うでしょう。ところが、実はイスラエル人だったというのは、まさに鏡であるわけです。先ほど、パレスチナ人とユダヤ人の家族のルポルタージュの話をしましたが、結果的に彼らの日常はすごく似ていたのですね。ですから、パレスチナ人やユダヤ人に対する先入観を壊して、意識を変えることもできるでしょう。
――テカイアさんは、エレーナを演じるにあたってどのようなことを心がけたのでしょうか。
ミリアム・テカイア:これは監督の妻でなかったらもらえないような役です。だから、絶対に私でなければできない、私が一番よくわかっていると自分を納得させられるまで、エレーナという人物を追求しました。ロシアからいつ移民したのか、入植地はどういう状況になっているのか、ひとつひとつの動作について、エレーナだったらどうするのか、すべてを細かく理解し、噛み砕き、エレーナが私なのは当然だと思えるところまで突き詰めました。
――監督はこの映画の登場人物をマージナルな存在というように表現をされていました。だからこそ、背後にある大きな力を想像させるところにも意味があるように思います。
エスティバル監督:まさに私もそういうことを言いたかったんです。こういう紛争のなかには、ベースとなる人間のレベルというものがある。マジョリティの人たちは沈黙して、なんとか生きていかなければならない。いわば、犠牲者であるわけです。政治的な理論による紛争の裏には、謙虚に、普通に生活したいと願っている人たちがいることを見せたかったのです。
マージナルな立場にこだわり、そこから他者を理解し、受け入れていく。『ガザを飛ぶブタ』には、エスティバル監督が、紛争の当事者ではなく、パリやウルグアイで活動してきたジャーナリストでもあること、そのアウトサイダーの視点と距離が最大限に生かされている。
聞き手:大場正明(映画評論家)
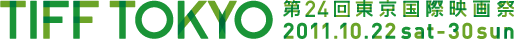

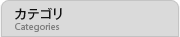

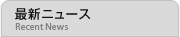




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
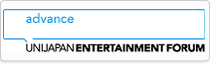

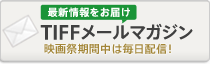
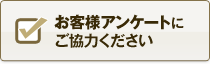

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)