【公式インタビュー】アジアの風 『飼育』
リティー・パニュ監督
+シリル・ゲイ(俳優)+ミシェル・フェスレー(脚本)
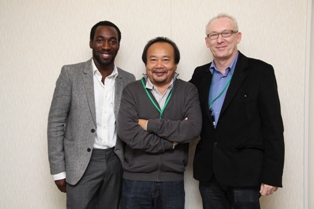
自らの体験を反映させ映画化した、カンボジア版『飼育』
カンボジア国内で100万人以上の死者を出したクメール・ルージュ(カンボジア共産党、1999年頃解散)。子供時代にその恐怖を体験したリティー・パニュ監督にとって大江健三郎の原作「飼育」は、1972年のカンボジアの村の子供たちを物語るために不可欠だった。原作は日本の山村が舞台で、時代は第2次大戦中だが、共通するのは村にアメリカの戦闘機が墜落し、乗っていた兵士が村の捕虜になることと、少年の目を通してそれが描かれる点である。
――主人公のポン少年は監督の分身ですか?
リティー・パニュ監督(以下、パニュ監督):いえ、私は町に住んでいたのでポンとは違います。でもいとこが農村にいて、アメリカ軍の爆撃を受けたという話を聞いていましたし、村でクメール・ルージュの兵士たちを多く見るようになったとも聞きました。クメール・ルージュはもともと革命を成し遂げようと思っていた。平等な社会を作ろうとしていた。それがなぜあれほど暴力的になっていったのか。子供たちをどんどん教化し、子供たちの方も教化されていった。そのことを描きたいとずっと考えていた時に大江健三郎の小説に出会ったのです。大江健三郎は「飼育」だけでなく、反戦思想についても大変興味がある作家です。

――大島渚監督の映画化した『飼育』は?
パニュ監督:見ていません。大島の映画は『愛のコリーダ』や『戦場のメリー・クリスマス』『青春残酷物語』を見ているのですが・・・。
――子供たちはどのようにキャスティングして撮影に向けて準備していったのですか?
パニュ監督:まず、撮影にふさわしいカンボジアの村を見つけました。それから町の学校、子供用のダンス・スクールなどで子供たちを探したのですが、いい結果が出なかったので、村で探すことにしました。農村の子供たちは学校に行っていないので、脚本を渡しても文字が読めません。セリフは口うつしで覚えさせました。本撮影に入る前にテスト的に短いシークエンスの撮影をして子供たちの様子を見ました。みな素晴らしい子供たちです。学校に行って勉強する機会が与えられれば、将来さまざまな仕事につくことができるのに、本当に残念です。子供たちはアメリカ軍パイロットを演じたシリル・ゲイともいい関係を持ったと思いますよ。シリルに訊いてみましょう。
シリル・ゲイ:今までの経験では子供というのは要求された通りにきちんと演技できる子とそうでない子に分かれるものですが、村の子供たちはテレビも映画も見たことがないので、とても自然で人間的でしたね。

――フィクションと現実を混同する子はいませんでしたか?
パニュ監督:いいえ。彼らは12、3歳なので戦争のことは知りませんが、自分たちの日常を演じればいい。たとえば川で水をせきとめて掻い出し、魚を素手で捕まえるとか。そういったことは町の子にはできませんからね。
――ポンはだんだん暴力的になり、子供たちのあいだで権力を持つようになりますが、演じた少年がそんな風に変化したりは?
パニュ監督:そうはなりませんでした。ポン役の少年は優しい子でした。カニを捕ってくると、みんなに分けていました。農民はそんな風に自分のものを分け与えるものです。少年は休憩時間はよく笑い、本番になるとすぐ気持ちを切り替えてポンを演じていました。
――この映画のラストは原作を離れて、ポン少年がクメール・ルージュの兵士たちと出発する光景が描かれます。少年の旅立ちというシンボリックな印象を受けますが…。
パニュ監督:時代は72年でした。そのことが重要です。78年に起きた大虐殺の予感はまだありません。クメール・ルージュはそれほど暴力的にはなっていませんでした。そして革命は正義だと少年は思っています。ただ、そのことを予感させる出来事は映画の中で描いたつもりです。ジャガイモを蓄えていた若い夫婦がジャガイモを取り上げられ、自己批判をさせられる場面がそれです。また、祖母は少年に口を利かなくなる。祖母はクメール・ルージュがやがて暴力的になることを知っていたのですね。しかし、少年は純粋に正義を信じていたのです。

――子供の頃、監督はリハビリテーション・キャンプでクメール・ルージュの再教育を受けますが、家がブルジョワ家庭だったからですか?
パニュ監督:というよりインテリの家だったからでしょう。多くのインテリ家庭がそうした目にあいました。
――15歳でそこを逃亡するまで、一番辛かったのは?
パニュ監督:死と隣り合わせの毎日を送ったことです。1972年から1975年までは戦争による死の恐怖、75年から78年まではクメール・ルージュによる死の恐怖がありました。
※ ※ ※
祖国を脱出した後、フランスに到着したパニュ監督は国立映画学校で学び、ドキュメンタリーで多くの受賞をする。インタヴューの終わり近くに脚本家のミシェル・フェスレーがやってきたので脚本作りについて質問。
ミシェル・フェスレー:脚本を書く前に監督とよく話し合いましたし、まずふたりで大江健三郎の原作を読みこんでいきました。深く、丁寧に読んでいったのです。意味をよく考えながら。そして互いに十分話し合いました。脚本は一緒に書いていきました。それぞれ別に書くというやり方ではなく、本当に一緒に書いていったのです。

聞き手:田中千世子(映画評論家)
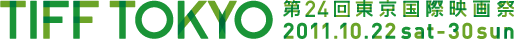

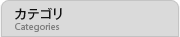

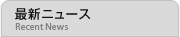




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
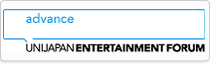

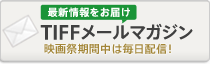
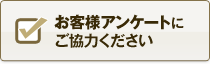

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)