第24回TIFF 日本映画・ある視点部門に出品の監督3人による座談会をお届けします!
出席者:
松江哲明監督:『トーキョードリフター』
杉田協士監督:『ひとつの歌』
小林啓一監督:『ももいろそらを』

©2011 TIFF
──今日は〈日本映画・ある視点部門〉に選ばれた3人の監督にお集まりいただきました。小林監督は『ももいろそらを』、杉田監督は『ひとつの歌』がはじめての長編作品であり、松江監督は『ライブテープ』(2009)で作品賞を受賞して以来の2度目の選出です。まず、映画祭に出品された作品を撮ろうと思ったきっかけは何ですか?
小林啓一監督(以下:小林):これまで映像の仕事をしてきましたが、自分から発信することはありませんでした。誰にも指図されることなく、いちど自分の作品を作ってみたいと思いました。

──これがはじめての脚本ですか?
小林:最初のホンは、お金がかかりすぎるという理由で没になりました。『ももいろそらを』とは近い話ですが、設定が違います。最初に監督するなら、女子高生ものをやりたいと思っていました。
杉田協士監督(以下:杉田):池袋の映画館シネマ・ロサの勝村支配人が、「作ったら公開するから1本撮りなさい」と声をかけてくれたのがきっかけです。脚本を書いたら文化庁の助成が決まり、話がどんどん膨らんでいったのですが、逆に助成金を受け取るために必要な総製作費が集まらなくなって頓挫しました。ある製作会社が付いていましたが、離れてしまいゼロになってしまったんです。そこで、いったんは放心状態のようになりましたが、自分自身が見たいと思う映画を、低予算でも作ろうと思い直しました。そんな中、勝村さんが「どんな映画でもいいから作ったら、うちで公開するよ」と言ってくれたので、もう一度踏み出すことができました。

──助成が決まった時点の脚本とは内容的に変わりましたか?
杉田:台本はかなり変わりました。話は一緒ですが、アプローチが全く違うものになりました。当初は、セリフが山ほどあったんです。
──松江監督は『ライブテープ』に続いて、再び前野健太さんとタッグを組んだ作品ですね。
松江哲明監督(以下:松江):3月11日の地震が起きた時、僕は韓国にいて23日に戻ってきました。戻ってきてまず思ったのは、東京が暗いということで、33年間生きて一番暗い東京だと思った。ヨーロッパに行くと暗くて当たり前じゃないですか。その感じに近い。商店の明かりも控えめで、すごくいいなあと。でも、世の中は明るい東京に戻そうという声が多数で、複雑な気持ちが込みあげてきた。4月11日に高円寺で大きな反原発デモがあり、遠巻きに見ていたら、すごく盛り上がっている一方で、「抗議するなら東京電力ができた時にやれよ」と、野次を飛ばす人もいた。これからの日本は大きな声で物事を伝えていくような国に変わるのかと思って、家に帰りニュースを見ると、都知事選の開票日で石原慎太郎さんの当選が決まって、ニュースキャスターが「30年以内に東京に大地震が来る確率は70%です。ぜひ石原さんには強い東京を作ってほしい」と言うのを聞いて、違和感を覚えました。
震災後の社会と内的テーマ
松江:1000年に一度の巨大地震が起きて、強いということが通用しない世の中になったと気付くべきなのに、また、強いものを作ろうとしている。未来を担う子どもたちに同じ価値観しか残せないのか。違う生き方を見つけるいい機会なのに、それは嫌だなと思って、前野健太とライブテープのスタッフに声をかけ、5月に撮影しました。地震の後もずっと前野さんの歌を聴いていて、「あたらしい朝」に、「僕のおじいさんの そのおじいさんの おじいさんの おじいさんのおじいさんは あたらしい朝日を見て何を思った」というフレーズがありますが、自分を起点にして未来と過去を思うことが、震災の前と後ではまるで違う聞こえ方がしたのです。
──小林監督の『ももいろそらを』は、製作中など、震災の影響という事はありましたか?
小林:昨年の10月23日に撮影に入り、12月28日に撮了しました。3.11の時は編集に入っていて、こんな時に映画を作っていていいのかと自問自答する事はありましたが、配給先も決まっていない状態で、映画祭などに選出されなければ見てもらえない。とにかく作品を仕上げて、アピールしていくことが先決でした。自分なりに伝えたいテーマがあって、地震の影響というのはありませんが、いま受け止めてもらえるのかが一番関心があります。
──伝えたいテーマとはどんなものでしょう?
小林:自分の目でものを見るということです。いろいろな固定概念とか価値観があると思いますが、自分の目でものを見ていない人が多い。自分も正直言ってそんな部分はありますが、自分の目でものを見るのと、自分らしく生きるというのは、イコールになると思うのです。「緊急時に、そんなつまらんこと言うなよ」と言う人もいるかもしれませんが、一所懸命作った作品なので、ぜひ見てほしいと思います。
──小林監督もそうですが、杉田監督も今回が映画祭初エントリー、初選出です。
杉田:自主製作で未公開の作品(『河の恋人』・2006)はありますが、本格的にはこれが第1作目です。ドキュメンタリーの作品も含めて、自分にとってテーマになってきたのは、誰かにとっての大事な存在が、ある日突然いなくなっても続いていく、その残された人の時間です。気がつけば、これまで作ってきたどの作品にも、根底にそのテーマがあります。『ひとつの歌』というタイトルは、そこからも来ています。ひとつの歌を自分は歌い続けているのではないかと。
──製作時に震災の影響はありましたか?
杉田:『ひとつの歌』は、震災が起きた時点ではすでに完成していました。この作品では、街のなかがよく映ります。駅や国道沿いなど、なんでもない場所に主人公がいて、多くの人たちとすれ違います。僕は、東京の多摩市に住んでいますが、震災が起きてからの数日間には、それまでにない感覚を持ちました。街ですれ違うすべての人が、おそらく同じ恐れを抱いている。目が合えば、会釈をしてしまうんじゃないかと思えるくらい近くに感じました。『ひとつの歌』を撮影していた2010年の夏には、道ゆく人たちがそれぞれ何を考えているのかなんて、分かりませんでした。そんな頃もあったなと、もう戻れない、過去の時間を懐かしむような作品になるのではと思いました。
今年の夏になって、子どもたちが再び公園で遊ぶ姿を見かけるようになった頃、ほとんど同じようなロケ地で、同じスタッフで短編映画を撮ってみたんです。『ひとつの歌』にも出演している枡野浩一さんが震災前後にツイッター上で発表して、話題を集めて刊行された詩集を朗読しながら街を歩いて、親しい友人たちにその詩集を届けに行くという内容です。聞こえてくる音も、映る人たちも、『ひとつの歌』の時と変わらないように感じました。これはなんだろう、と。それこそ公園の草や木にレンズを向けても、そこには草や木しか映りませんし、駆けている子どもの姿は、ただ駆けている子どもとしてしか映りません。見えないものは映らないという、映画を作る上で分かっていたはずのことが、これまでにないくらい迫ってきました。その見えないものに、今後どう向かって行くのかについて、いま、考えています。
東京と千葉──街を切りとる
──松江監督の『トーキョードリフター』は、前作のように1カ所ではなく、新宿、渋谷、多摩川縁とさまざまな場所でロケしていますね。
松江:東京をひと月半ロケハンしましたが、この期間が自分にとっては大切でした。スタッフの中には、いま作るべきじゃないという人もいたり、実家が仙台にあって車が流された人もいます。家族を東京から避難させている人もいました。いろんな考えのスタッフとともに、意見を交わし、とにかく僕らは暗い東京を肯定したかった。誰も撮らない、被災地としての東京の姿を。そこで考えたのは、もともと電気が点いていたのに、いまは消えている場所です。銀座や六本木、東京タワーにも行きましたが、風景はいいけど合う歌がない場所ははずしていきました。明大前に行ったのは、前野さんが昔住んでいた場所だからです。

──小林監督はこれまでテレビやミュージックビデオの仕事をやってきたわけですが、やはり映画を撮りたいという思いはありましたか?
小林:何となくですが、いつも思っていました。ドキュメンタリー、ライブ撮り、CMなどさまざまなことをやりましたが、テレビドラマと映画はやったことがなかった。大学も普通の大学で、最初から映画の世界に憧れていたわけではないけれど、仕事をこなすうちに、そんな気持ちが芽生えてきました。
──『ももいろそらを』では、主人公の女子高生が新聞記事を採点します。これはどんなところから着想されたのですか?
小林:喉が痛くて病院に行った時に、待合室で何となく思いついたのです。
──映画第1作ということで、ロケハンにも気を遣ったのではありませんか?
小林:撮ったのは東京、千葉、埼玉で、物語の設定は千葉のある街です。最初に千葉県警の派出所が出てきますが、厳密にどこの街とは説明しなくてもいいと思いました。
松江:でも東京じゃない街の話という部分は、強調してますよね?
小林:東京の子たちの話はたくさんあるし、地方の子たちの話も相応にある。僕は千葉の埋め立て地で育ちましたが、そこは誰も取り上げてくれないような街です。そうした中途半端な場所をクローズアップするのもいいと思いました。東京に足を伸ばすこともできるし、誇れるほどの田舎でもない。そこで暮らす高校生たちの日常を描いてみたかった。

ケータイもパソコンもない
──杉田監督は、これまで篠崎誠、黒沢清、青山真治など多くの監督の下で助監督につきましたが、その経験は監督をする際、役に立ちましたか?
杉田:助監督をしていると、現実的な作業に対する反射神経が養われます。『ひとつの歌』は、僕を含め5人のスタッフで撮ったのですが、無意識レベルで役に立つというのはありました。ただ、監督としてはそれぞれ当人にしかできないことをやっていて、まったく参考にならないです(笑)。近づきすぎるとよくわからなくなるので、ある段階から、もう離れた方がいいのではと感じるようになります。

──今日のフィクションでは珍しいことに、『ひとつの歌』には携帯電話もパソコンも登場しません。主人公の青年は携帯ではなく、ポラロイドで写真を撮り続けます。
杉田:別に意識したわけではありませんが、そうなっていました。単純な要素で映画を撮ってみたいというのがあって、今回はポラロイドカメラで写真を撮ることで、この映画のアクションを生み出せればいいと思いました。
松江:あの映画で携帯やパソコンが出てきてしまうと、いろんなものが壊れてしまいますよね。逆に、すごくうまい使い方をしている作品もありますけど。
杉田:例えば、ジョージ・A・ロメロの『ダイアリー・オブ・ザ・デッド』とか大好きですが、自分ではやれません。映画の嗜好と作る映画が違うんです。何でだろうっていつも思うのですが(笑)。ジョン・カーペンターとか、トビー・フーパーを観て育っているのに、なぜそういう映画が作れないのか。『ロボコップ』なんか大好きだったのに。いつかやってみたいという思いはあります(笑)。
松江:僕の場合、ドキュメンタリーからアイデアを得ることは、実はほとんどなくて、ハリウッド映画とか観て、いいと思ったものを元ネタにしていたりする。ドキュメンタリーは現実を問うものだから、やっても絶対マネにならないので。でも恥ずかしくなる時もありますよ。モロにやっちゃったな、バレないかなと(笑)。

──小林監督の映画体験はどんなものでしたか? 影響を受けた作品はありますか?
小林:僕は、この仕事を始めてから映画をよく観るようになったので、子どもの頃は『スター・ウォーズ』とかでしたね。仕事として関わるようになって、影響を受けたりしましたが、マニュアル化してしまうことも多いので、自分の作品ではそういうものを取り払って作りたいと思ってます。
作品評1──ももいろそらを

──皆さんにはそれぞれの作品を観ていただきましたが、これからは各作品に対する率直な感想を聞いていきたいと思います。まず、小林監督の『ももいろそらを』は、主人公の女子高生いずみが財布を拾ったことからはじまる青春ものです。長回しを駆使して、3人の女子高生の日常をリアルな息遣いで描き、思春期特有のほろ苦さを見事に表現しています。初監督作ということで苦労した点はどんなところでしょう?
小林:8月から10月にかけて念入りにリハーサルを行い、女子高生役の3人には、表情や仕草など時に細かく指示しました。撮影については、今回、自分でやっているのであまり器用なことはできません。自分の視点で主人公を追いかけるだけで、技法的なこだわりはありません。ただ、切り返しで撮るのはやりたくなかった。フィクションだから的確なカメラ位置が保てるわけで、わざわざそこにカメラを据えず、切り返しで撮るのは自分の中では釈然としない。使用したのが高画質カメラで顔もよく映るので、あとは見てくれるのではないかと思います。
──松江監督、杉田監督は『ももいろそらを』をどうご覧になりましたか?
松江:うまい下手じゃなくて、あの子たちが映画の中でちゃんと生きている感じがしました。リアルかどうかはどうでもよく、あのセリフ回しが成立する人たちなんだと。そういう映画は観たことがなかったので面白かったです。僕は映画の中の3人に興味をもって、インターネットで検索したのですが、実際の彼女たちは全く違うんだろうなと思いました。でも、映画の中のあの子たちは、すごくいいなと思いました。実際に、ああいう喋り方をするかはどうでもいい。思い出したのは神代辰巳さんの映画で、『黒薔薇昇天』では登場人物がずっと観覧車を乗り継いだりして、実際にあんな動きをすることはないけれど、それが成立するようにちゃんと作ってある。物語ではなく、キャラクターで引っ張っていくところに強みを感じました。
杉田:観始めた時、セリフの情報量が多くて、どんどん押し寄せて来るぞと思ったんですが(笑)、段々そう感じなくなっていくのが面白かったですね。正直、最初は僕が苦手な映画だと思って見ていましたが、気にならなくなっていました。フォーカスはすべて人に当たっていて、街があまり映らない。徹底的に人に寄っていて、観ていると、登場人物の全員に愛着が湧いてくるんです。主人公にお金を借りるおじさんとか、ボーリング場で「写真撮って」と言う女の子とか、出演シーンの少ない人たちも妙に印象に残りました。終わる頃には、どうしようもない人も含めてみんなのことが好きになっていて、なんか悔しかったです。実は、僕もネットで役者の皆さんのことを検索しました(笑)。
──モノクロの画面が印象的ですが、一部着色は考えませんでしたか?
小林:まずなぜモノクロにしたかというと、主人公はもうしばらくすると滅茶苦茶になってしまうのです。把握しきれないことが多すぎて。でも、そこを撮っても面白くないので、そうしたことも考えて、冒頭で2035年という設定しました。2035年のいずみの想い出話だからモノクロにしました。例えばピンクの空というのは、それほど重要なファクターではなく、女子高生たちの行為と、それに対する男の子のリアクションが大切なんです。
作品評2──トーキョードリフター

──松江監督の『トーキョードリフター』は、震災下の暗い東京の街を、フォークシンガーの前野健太さんがギター1本と、バイクで移動しながら歌って回る作品です。前作の『ライブテープ』は、74分ワンカットで吉祥寺をロケし、さまざまな仕掛けで話題になりましたが、今作ではまったく別のアプローチになっています。
松江:『ライブテープ』では、前野さんをクローズアップしましたが、今回は劇中で、「前野さん」と呼びかけることもなく、カメラワークもどこで何を歌うかも全部決めたので、自然とそういう作りになりました。前野さんにはこういう気持ちで歌ってと、意図を持って伝えています。もしかしたら前野さんは今回、役者のつもりで参加したのかもしれません。撮影の近藤龍人君には、この映画は完成度よりも現在性を優先したいと伝えました。韓国ではyoutubeにアップされた被災地の映像ばかり見ていましたが、携帯のカメラで撮ったものに今を感じた。NHKのカメラも、物凄い望遠で原発の煙が出ているのを撮っていて、きれいに撮られた映像よりもインパクトがあった。
そこでピントがぼけようが、色味が変わろうが、オートフォーカスで行こう、と。そういう映像でなければ、観客に届かない、対話できないと感じていました。その上で、彼がレンズを持ってきた。前作がフォーク系の映像だとしたら、今回はスタッフのジャムセッションみたいなもので、僕の中ではこれまで撮った中で一番フィクションに近い作品です。
──では、小林監督と杉田監督は、『トーキョードリフター』をどうご覧になりましたか?
小林:変わってますよね? こんな映画が存在すること自体、面白いと思いました。自分が思い描いている映画とはまったく別物なので、正直、感想を聞かれてもよくわからない。今まで観ずに過ごしてきただけかもしれませんが、はじめてこういう映画があるのだなと知りました。
杉田:SF映画みたいな印象を持ちました。一見、街をテーマにしているようですが、松江さん実は街に全然興味がなくて、前野健太さんだけを見ていたいんじゃないかと思いました。109の前で撮影しているのに、奥まったコーナーに追い込んで撮っている。普通だったら、ネオンの消えた全景を入れて撮るんじゃないかと思います。でも、松江さんは安易にそれをしないで、ひたすら前野さんを追いかけていく。その潔さが好きでした。
松江:そこちょっと違うんです。引いて全体を撮ることが、必ずしもその場所ではないと思っていて、僕の普段の映画の作り方がそうなんです。絵のサイズのことだけではなく、狭い空間を凝視することでフレームの外を想像させたい。スクランブル交差点を囲む大型ビジョンも映していませんが、僕も近藤君もそうしたものは撮りたくない。はじめに被写体ありきで、被写体が動かないかぎり、カメラが勝手にパンしちゃいけないというのが僕と近藤君の鉄則なのです。
杉田:あのバイク、取り締まられないのかと心配になりました。すごい場所に止めたなって(笑)。

ドキュメンタリーを作るということ
──小林監督も杉田監督もドキュメンタリーの経験がありますね。小林監督はテレビ番組「情熱大陸」で、かつて北島康介さんを撮られたそうですが。
小林:バルセロナで世界水泳が開催された2003年のことです。北島さんが金メダルを獲る前の年(翌年のアテネ五輪で受賞)で、タイムがすごく伸びている時期です。ドキュメンタリーでは体力と精神力の他に、現場での駆け引きがつねに要求されますよね。「情熱大陸」の時、僕のひと言で北島さんのタイムが落ちたらどうしようと思いました(笑)。北島さんはあっけらかんとしていて、実際にはまったく心配なかったわけですが、監督というのは、時にネガティブなことも言ってしまうと思うんですよ。
松江:ありますよね、面白いものを作るためには。
小林:ちょっと意地悪な質問を思いついたりする。そうすると、僕が言ったひと言によって、みんなが期待してないものができてしまう恐れがある。ドキュメンタリーではよくそういうことが起こる。そんなふうに他人の生活に介入するのは恐怖であり、本当にいいと思った対象しか作れないなと思いました。松江さんはそこで勝負しているんだと思います。
松江:そうでもないです(笑)。いいものを作るというよりも、むしろフラットでいたいんです。テレビだと、こう作ろうとあらかじめ決めて作ることが要求されますよね。関わる人が多いほど、多くの説明を求められる。でも、ドキュメンタリーが面白いのは、そうは行かない時です。最初の予想からズレていくところに、醍醐味がある。そのためにネガティブなことを言ったり、回さないでと言われた時でもカメラを回すんです。
小林:そこには嫌な感じもありますけど、いいと思ったから撮るわけですよね?
松江:そうですね。まず被写体にとっての良し悪しは、二の次にしないといけない。他人の人生に影響を与えて傷つけてしまうわけで、その意味でドキュメンタリーの監督は、被写体とは一生付き合わなければならない。作品は残るのに、被写体が上映しないでと言うかもしれない。自分がいいと思うことを、必ずしもよく思ってくれるとは限らない。だからこそ、よい緊張関係が生じ、面白いものが撮れるわけです。でも正直、怖いという気持ちもあります。
──杉田監督はどんなドキュメンタリーがお好きですか?
杉田:段取りとかも含めて、作り込んだ作品が好きです。被写体に事前に契約書を書かせておくフレデリック・ワイズマンとか。最近では奥谷洋一郎監督の『ニッポンの、みせものやさん』がよかったですね。日本に唯一残っている見世物屋さんを10年かけて追った作品です。見世物屋の世界では札幌が聖地らしいのですね。むかし札幌のお祭りに行くと、日本全国から見世物屋が集まって賑わったそうです。その流れで、札幌に向かう見世物屋の人たちを奥谷監督は撮っていて、トラックに同乗するんですが、普通だったらお邪魔するわけだから、3人シートの真ん中の盛り上がった部分に座るはずです。
でも奥谷さんは助手席に座って、見世物屋のふたりをひとつのフレームで撮っている。立場的にそれはないと思うのです(笑)。長距離の移動なのに、年老いた座長が真ん中の狭いスペースに座っている。映画を撮るためにそのように座らせたわけで、被写体とそういう関係を築けているというのが心に響きました。
松江:共犯関係ですね。被写体に遠慮した途端、映画としてのクオリティは下がるわけで、たとえ社会のルールは通用しなくても、被写体と関係が築ければ、社会を超えた規範ができる。映画はそこまで行かないとダメですよね。僕の場合、前野さんもスタッフも飲み仲間ではない。映画を撮る時だけの付き合いですが、表現の方向性は似ている。これはインディペンデント出身という共通項があるからで、録音の山本タカアキさんも撮影の近藤君も映画学校出身で、いざとなればHi-8で映画を撮れるという感覚がある。前野さんのような音楽をやっている人も一緒で、自主製作でCDを作り、ギター1本で日本全国をライブで回って歌う。だからすごくいい関係です。ドキュメンタリーに限らず、映画というのはひとつの作り方なんだと思います。
作品評3──ひとつの歌

──杉田監督の『ひとつの歌』は、駅のホームである事件に遭遇した寡黙な青年が、やがてその被害者の娘と心を通わせ、ある告白をするまでの物語です。説明的な描写を廃し、また犯人らしき人物との心理劇や逮捕劇といったありがちなパターンにもはまらない、不思議な味わいの作品です。
杉田:脚本は12頁ほどの短いもので、ロケハンの時、「これしかないのに何をすればいいの?」とスタッフに怒られましたが、役者が入り、実際に動いてもらわないとわからないと思っていたので、ずっと「当日にならないとわからない」と言い続けてきました。その分、エチュードではなく、演技の段取りはすべて決めるようにしました。現場では、もうちょっと説明的なことを足した芝居もやってもらったりもしましたが、少しでも説明的になるとしっくりこなくて。なぜそうなのか議論しました。映画にとってではなく、今回集まったメンバーにとって、なぜしっくり来ないのかが重要でした。毎日議論を重ね、その線引きをどこにするか、見つけていきました。
──松江監督はこの作品をどうご覧になりましたか?
松江:スタイルがちゃんとできている映画ですね。1本目からそういうのができている監督が最近多くて、明らかに映画でしかできないことをやっている。1本目でそれができるところはすごいと思いました。でも、そこに疑いが出たらどうなんだろう。やはり、こう撮るという意図があったわけですよね?
杉田:実はなかったんです。例えば、カメラ位置など僕はひとつも決めていません。芝居と段取りを決めただけで、撮影の飯岡幸子さんに後はすべてお任せしました。僕が見たい時間を段取りとして作ったら、飯岡さんをはじめとするスタッフがそれを映画にしてくれる。編集も自分ではやっていないのですが、撮影・録音・編集の3人が力を出したことで、一貫性のある作品に仕上がったのだと思います。僕も思う存分芝居に打ち込んで、こういう時間が見たいと伝えました。こうした形で思い切りやってみたかった。そういう意味では、スタッフそれぞれがぶれない自分の軸を持ってこの作品に向かったので、結果的にスタイルが確立したのかもしれません。
──スタッフは今回が初めての人ですか?
杉田:録音の黄永昌さん以外は、すべて初めて組んだ人たちです。今後、同じやり方をするかというと、それはわかりません。
──小林監督はどうご覧なりましたか?
小林:静かな映画だなあと思いました。話を聞いてそうかと思ったのは、こういう時間を見たいということで、なるほどと思いました。自分の場合、どうしてもキャラクターに目が行ってしまうのですが、これはそういう映画じゃないですよね。あとこれは東京の設定ですか?
杉田:東京の武蔵野です。
小林:東京の郊外には、ああいう時間が流れてるのかと思いました。前半、主人公の青年はほとんど喋りませんが、無口な人間を据えて映画を撮るというのが自分にはよくわからなくて、一体どう演出しているのか気になります。歩く場面ひとつ取っても、ただ「あそこまで歩いてください」と言うのか、「何かを思いながら歩いてください」とやるのか。そもそも、12頁しか脚本がないわけですよね(笑)。
杉田:でもデジタルカメラでだいたい17時間くらいは回しています。バイクに乗るシーンだけでも3時間くらいはある。ふつうなら怒られる撮り方ですね(笑)。
デジタルか、非デジタルか
杉田:ただ、僕が自主映画を始めた時、もう周囲の環境はデジタルでした。助監督でカチンコを打つのですが、フィルムの現場はほんの1〜2回だけ。もともとデジタルに慣れ親しんできました。
松江:90分の映画で、17時間というのはそれにしても長い。ちょっとないですよね? でも、フィルム以外の機材で映画を作るなら、ぼくはフィルムと同じ作り方はしたくない。最近のデジタルは画質とか、フィルムに近づいている感じじゃないですか。僕はそれが嫌で、だったらフィルムで撮ればいい。
杉田:それは作品を観て強く感じましたね。すごく潔い。
松江:デジタルでしか撮れないもの、ビデオでしか撮れないものってあると思うんですよ。その上で、映画でしかできないことを意識します。
──そうすると脚本を書く場合、どんなカメラを使うかを想定して書くこともありますか?
杉田:書いている時は、撮影部も決まっていないのでないですね。
松江:僕の場合、A4のペラ1枚ですが、用意しました。映像の質感をペラペラなものにしてみたかった。奥行きを出さず、風景に溶けてる感を出したいと。全部にピントが合っているか、ぼけているか。そんなビデオでしかありえない映像にこだわりたかった。近藤君はいろんなアイデアを出してくれて、バイクに乗る場面や渋谷の場面では、スノボやサーフィンをやる人がよく使用している、すぐユーチューブにもアップできるおもちゃみたいなカメラに、ドンキホーテなどで500円で売っているレンズをテープで括りつけて、「この方が松江さんの意図に近い感じになりますよ」と見せてくれた。近藤君は撮影部からの視点で演出を考えてくれました。
小林:僕は自分で撮影しましたが、フィルムについてのこだわりはありません。海外の作り手はフィルムをガンガン回していて、日本はその時点でもう負けている。海外はルックもきれいなうえ、演技もしっかりしている。バジェットの違いなのかもしれませんが、それは作り手だけの理由で観ている人には関係ない。きれいな画像が好みなので、きれいに撮れる機材であれば、僕は問題ありません。
映画作りに対するそれぞれのアプローチ
──最後に、いま日本で映画を撮って観客に見せることについて、皆さんはプロとして、どんなことを考えてますか? 表現者としては3人とも完成しているように思いますが、観客に見せる枠組みも含めて、今後どうしていきたいのか。
小林:たぶん年齢ともに、自分の中のテーマは変わっていくと思います。それをどう見てもらうのかというのを、自分の中で模索していきたいと思います。もちろん、作った作品が少しずつ観客に受け容れられ、広がりが出てきたら嬉しい。芸術性というのはあまり考えていませんが、今後も練りに練った上で作品を実現したい。
松江:自分が最近好きな映画は、完成していない映画です。震災以降、映画的にいいか悪いかはもう通用しないんじゃないでしょうか。それは作り手の気持ち、スタイルや技術でしかなくて、もっと違ったものを模索しなければならない。今年観た中で好きな映画は、監督不在の『LIFE IN A DAY』でした。これはユーチューブで募集をかけて、一般の人が撮った日常の映像を集めたもので、まとめかたには疑問があるけど、映っていることやコンセプトは現代的だと思います。バンクシーの『イグジスト・スーパー・ギフトショップ』もそうですが、監督自らが映画を疑っていて、映画じゃないものが映画になってしまうというのが現代的で、僕は今そういうのに興味があるんです。できれば、自分でもそういう映画を続けていきたいのですが、続けるにはインディペンデントでないと難しい。
でも、インディペンデントで有り続けるのは容易じゃない。第一、自分がやっていることにも疑いがあるし、そんなふうに作っていても、ダメだろうなというネガティブな気持ちもある。最近、インディペンデントにこだわり、僕と同じような立場でやっていた大事な人が亡くなってしまい、彼がいなくなったことで、自分がインディペンデントにこだわりを持ってやっていくことはもうできないと思ったのです。映画を作り続けたいし、一緒にいる仲間も大事だし、この映画を通して出会う新しい観客も大切にしたい。でもそれを続けていてはいけないという思いもあって、自分の中で矛盾があり悩んでいます。
確実に言えることは、観客が求めているのは、僕が今いいと言った映像とは違うタイプのものです。地震の後、わかりにくいものはますます許容されにくくなった。それは言わなきゃいけないし、表現しないといけないことだけど、1800円を払って普通に映画を観に来る人は、もっとわかりやすいもの、強いものを求めるんじゃないかと思います。だからこそ、曖昧なものを表現したい。残るもの、共有できるものを提示したいという思いはありますが、それはどんどん薄まっていくだろうという気もします。ちなみに、次の映画は強いメッセージ性があるもので、何故そうなるのかと言えば、被写体がそうした人だから。僕は今を一所懸命生きようとは表現したくないが、その人を撮ることでそうした表現にも向き合える。そういう人と出会えるのが映画のいいところで、出会いがないと映画は作れない。だから人と会うこと、続けることを大事にしたい。1本1本の完成度より続けることで、出会える場所を作っていきたい。
杉田:映画に対する興味とアプローチは、監督として作品を作る時も観客として観ている時も、あまり変わりません。映画のワークショップを主宰していて、各地で出会った人と作品を作るのが好きですが(自分で監督するわけではありません)、松江さんと同じで、映画なんか作ってもまったくしょうがないんですが、でも集まって映画づくりをしていると単純に元気になれるんです。助監督をやめて、そうした活動をしてるのですが、僕にネームバリューがないので、仕事を取りつけるのに苦労するんですよ。だから監督としてちゃんと作品を作らないと、今後、自分がやりたいことも立ち行かなくなると思っています。
各地で出会った人たちに対して、自分はこんな作品を作るというのを観せたいし、そういう人たちに届くものにならなければダメだとも思います。ワークショップに来た人たちにこの作品を見せると、みんな「ふーん」と言って帰っていく。まだ、接点がないなと思っています。母にも怒られます。「こんな作品でお客さん大丈夫なの?」って。
松江:母親は強敵ですよ! 『ライブテープ』を観せた時も、なんかボーっとしていました。作品賞を受賞してもウチの母親には届かない(笑)。『トーキョードリフター』も映画祭に観に来ると言っていますが、不安もあります。でも母親に向けて表現しちゃうと、自分の中で負けになる。しかし、母親にとっては作品よりも、新聞に出たことのほうが大きくて、新聞記事は大事に取ってあるのに、もう一度作品を観たいとは言いません。
杉田:離れているように見えて、実は一周して近づいていたというふうに、いつかならないかなと思っています。狭くてもいいから通じたらいいなと。札幌の人たちと昨年、映画を作って、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭に出品したんですが落ちてしまった。プロじゃない人たちが集まって、苦労しながら映画を作ったものの、公の場所で上映する機会をつくるまで、まだ持っていけていません。そうしたところに出て行けるまで、力をつけたいと思っています。
小林:映画祭で話題になれば、多くの人に観てもらえる。これは自分の目でものを見るのとは矛盾していますが(笑)。でも、まず観てもらうためには、自分自身がチャレンジして、大きな舞台に立つことです。やりたいことはたくさんあるから、これからも映画を撮り続けたいと思います。
日本映画・ある視点部門 上映作品予告編
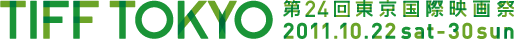

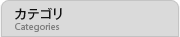

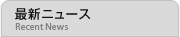




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
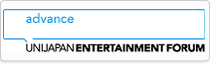

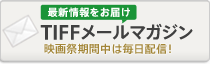
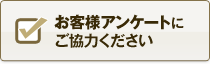

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)