10月25日(火)、コンペティション『ホーム』の上映後、ムザッフェル・オズデミル監督が登壇し、Q&Aが行われました。

Q:自伝的内容作品だとお伺いしましたが、いつ頃から映画にしようと考えたのでしょうか。経緯からお聞かせください。
ムザッフェル・オズデミル監督(以下オズデミル監督):10年前までこの物語が映画になるとは思っていませんでした。人というのはその時々の魂の状態に応じてセンシティビティを決めていくのです。つまり時によって変わっていきます。20年間通い詰めていた山の崖がありました。その崖に氷を張っている時はその氷を踏みながら登っていました。ところが、15年前にその崖の氷が急速に溶けてしまったのです。もはやその崖には到達出来なくなってしまったのです。そういうこともあって私の中のセンシティビティが突然変わってしまったのです。その出来事から私は恋愛をテーマにしたような映画からは遠ざかるようになりました。『キル・ビル』のような娯楽がテーマの映画からも遠ざかるようになりました。ですので、私にとってのパラノイアなのかもしれません。実際は分からないのですが。
Q:この映画で使用されているロケ地についてですが撮影時期はいつごろからいつまでだったのでしょうか。またこのロケ地も実際に開発など、今日現在映画で観たような景色と変わってしまったところがあるのでしょうか。
オズデミル監督:この場所はわたしが生まれ、6歳くらいまでの幼少時代を過ごしたところです。街中や村にいくつか自分たちの家がありました。すべて同じルート上にあって、訪れる時にいつもルーティンで回っている場所なんです。撮影については花が咲くころから始まり、4月から6月の間に行われました。
Q:アナトリアの美しい風景と厳しい現実を堪能できましたが、アナトリアという土地はトルコの方にとって特別な場所なのでしょうか。
オズデミル監督:その答えはこの作品にあります。ドアンはゴミ箱を見ているわけで下には街があってその間にはトルコの国旗があります。その時ドアンは心の中でなんと言っていたか。言語では保守性というのはあたかも教会によって教会に遮られているようでした。つまり国旗によってということです。なぜか私たちはこのボーダーということを重視するんですけども、実際にはその中はあまり見ていないんです。

Q:主人公が山村で国の諜報機関による身分証明書の確認をされるシーンがありますが、これはトルコの現状としてあることなのか、監督が国からそのように見られているのでしょうか。
オズデミル監督:トルコの南東部にいるクルド人の戦闘士たちは、時々一人二人北部の山岳地帯にやってきて、不穏な状態を引き起こすことがあります。彼らはテロを手法に選んでいますので、人々はそれを怖がるわけです。ですので、諜報機関の方も仕方なく調査はします。一度、私自身の身にもこういったことは起きました。でも、私がよそ者ではないということがわかると、後から謝ってきましたよ。
Q:薬害で障害を持った男性が部屋から出ていくときに、主人公が後姿をずっと見送るシーンには監督の何らかの思いを託されているのですか。
オズデミル監督:腕のない男性ですけど、実は私の幼少時代の友達です。私にとっては一つのトラウマでした。ですので、初めて神について疑ったわけです。そして、疑いを持つということを考えたとき、そのことが感謝するという気持ちになることに罪悪感を覚えたのでした。
Q:トルコでは不十分な形でしか上映されていないとおっしゃっていましたが、これはどういうことだったのでしょうか。
オズデミル監督:上映については、その時まだ映画は完成していない状況だったのです。というのは、一つ二つシーンを削っていたのです。トルコである映画祭に出品する、そのあと東京国際映画祭に間に合うようにということで、急いで持ってきたのです。ですので、一般公開はされていません。
Q:花を摘んで、それを主人公が嗅ぐというのはどういう意味だったのでしょうか?
オズデミル監督:何かに一つの名前を付けるということは、それは一つのエチケットをそれにつけてしまうことになります。つまり、凡庸なもの、ごく当たり前のものにしてしまうということ、その存在性から切り離されてしまうということになります。ドアンが現地で幼少時代のころに体験したような呪いの魅力を失っていくとき、そのことにおいて花は一つのシンボルなのでした。存在し続けるということが自分にできなかったために、自分に対して罪悪感を感じ、そしてまた自分に対する敵意を心の中に持つようになっているのです。花を摘むということが、そもそも自らに害を与えるというようなものです。そもそもその匂いすらも失ってしまったのですから。
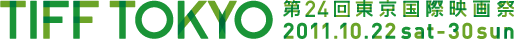

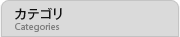

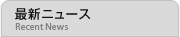




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
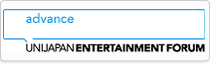

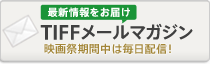
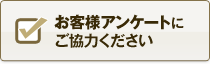

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)