【公式インタビュー】コンペティション作品『ヘッドショット』
ペンエーグ・ラッタナルアーン監督

アメリカのフィルム・ノワールへのオマージュとして、楽しみながら作った作品
タイ映画界に独自の地位を築き、国際的な注目を集めるペンエーグ・ラッタナルアーン監督。新作の『ヘッドショット』は、オリジナル脚本ではなく小説の映画化だ。その物語では、頭を撃たれ、世界が逆さまに見えるようになったヒットマンの現在と過去が複雑に入り組んでいく。この映画で東洋的なノワールの世界を切り拓いたラッタナルアーン監督に話をうかがった。
――Win Lyovarinの小説“Rain Falling Up the Sky”の映画化ということですが、この原作はタイでどのように受け止められていて、どうして映画化しようと思ったのでしょうか。
ペンエーグ・ラッタナルアーン監督(以下、ラッタナルアーン監督):原作者は私の友人でもあり、ミリオンというような大ヒット作を生み出すことはありませんが、根強いファンがいる作家です。この映画を作った後で、自分が思っていたよりも多くの読者がいることがわかりました。この原作は、映画そのもの、まるでフィルム・ノワールのように書かれています。もちろん映画化にあたって変更したり削ったりはしましたが、オープニングのシーンなどは原作そのままです。まさに映画にするためにあるような小説でした。
――小説のテーマにも関心を持たれたのではないかと思いますが。
ラッタナルアーン監督:テーマが“カルマ”であることは明らかです。何かをすればその報いを受ける。仏教徒の国なので、カルマはみんなの人生の一部になっています。それと、私が年をとったせいで、よりこのテーマに惹かれるようになったのだとも思います。
――監督の作品を振り返ってみると、『シックスティナイン』や『わすれな歌』といった初期の作品には明確なプロットがありましたが、『地球で最後のふたり』から、プロットではなく、映像のイメージやムードで表現するスタイルに移行しました。そうしたこれまでの作品の流れと、新作の違いについてはどのように考えているのでしょうか。
ラッタナルアーン監督:新作は私の監督作のなかで、個人的な世界から最も遠い作品の1本だといえます。『地球で最後のふたり』、『インビジブル・ウェーブ』、『Ploy』、『ニンフ』といった一連の作品では、非常に個人的な世界を扱い、実験的な映画にもなっていました。それが成功したこともあれば、あまりうまくいかなかったこともあります。この新作の場合は、原作者が他にいますし、私が好きなアメリカのフィルム・ノワールへのオマージュとして楽しみながら作った作品です。頭を使うのではなく、監督として培ってきたスキルを使いこなす、ある種の練習の成果ともいえます。

――アメリカのフィルム・ノワールというと、昔のモノクロ作品が思い浮かんだりもするのですが、映像に関してそういう陰影を意識したというわけではないのでしょうか。
ラッタナルアーン監督:ロケーションやデザイン、衣装などの準備を進めていたときに、色味が薄いものになっていったのですが、それは狙ったというより無意識にそうなったという感じです。この映画で主人公が辿る道はとてもダークで、映画の中盤で彼が僧侶になるときだけ、寺院や森の映像が束の間の心の平安を表わしています。その後は、またタフでダーティな世界になります。そうした構成からごく自然にあのような色合いになりました。
――『シックスティナイン』のエンディングには、トルーマン・カポーティの小説『カメレオンのための音楽』から、「神様が贈り物をくださる時は、同時にムチもお与えになるものだ」という一文が引用されています。監督は様々にスタイルを変えながら、一貫して因果応報や贖罪というテーマを掘り下げているように思えますが。
ラッタナルアーン監督:あのカポーティの言葉は、とても仏教的だと思います。良いことがあれば、悪いことがある。だから、良いことがあっても喜びすぎず、悪いことがあってもあまり落胆せず、中道を行くというのが仏教の道理です。新作の主人公は、自分のカルマから逃れることができない。たとえ仏教徒ではなくても、人間であれば誰にでもカルマはあるものです。この映画では、仏教的というよりも、人間的な視点からそのカルマを表現していると思います。
――この映画の主人公は、世界が逆さまに見えるようになりますが、それだけではなく、主人公に絡む登場人物たちがみな、最初に思っていたのとは違う人間で、それぞれに秘密を抱えていることが明らかになります。そんなふうに次々と世界がひっくり返り、主人公に拠り所がなくなったときに、本来の自分が見えてくる。そういう意味では、フィルム・ノワールであり、また自分探しの旅の物語にもなっています。
ラッタナルアーン監督:それは明らかです。すべてを受け入れているのです。
※ ※ ※
ラッタナルアーン監督はそれを意識していたわけではないようだが、『ヘッドショット』では、明確なプロットがある初期のスタイルと、『地球で最後のふたり』以降の心象風景を思わせるスタイルの両方が生かされている。ふたつが融合することで、奥行きや深みのある人物像や世界が生み出されているのだ。
聞き手:大場正明(映画評論家)
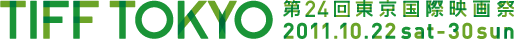

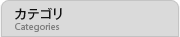

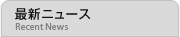




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
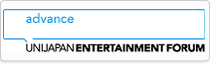

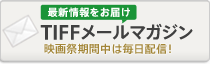
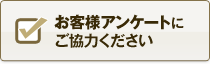

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)