【公式インタビュー】 コンペティション 『別世界からの民族たち』
フランチェスコ・パティエルノ監督

移民についての映画ではなく、イタリア人についての映画
イタリアにおける移民問題は、深刻の度合いを増している。ベルルスコーニ首相が排斥感情をあおるような発言を繰り返し、アフリカ系移民による差別への抗議デモも頻発。半面、その移民の労働力がイタリア経済を下支えしているのも事実だ。フランチェスコ・パティエルノ監督はそんな社会的なテーマを、イタリアから移民が消えてしまったらと仮定した風刺劇『別世界からの民族たち』として成立させた。
パティエルノ監督によれば、イタリアでの移民の比率は12%ほどで、北部にいくほどその割合が高まるという。『別世界からの民族たち』も北イタリアが舞台だが、発想の起点は、米のインディーズ映画“A Day Without a Mexican”(2004)だった。
「ロサンゼルスからメキシコ人が消えてしまうという映画からアイデアをもらいました。これをイタリアの今に当てはめられる可能性があると考え、イタリアの現実を語りたい、そして今の社会がいかに外国人、特に欧州の場合はEU圏以外の人を必要としているかを示すことができると思ったのです。さらに経済的な面だけではなくて、愛情という部分でも外国人を必要としているということも示したかった」
実際にイタリアで生活していると、移民の存在が欠かせないと感じることが多い。監督の6歳になる子どものベビーシッターもルーマニア人の女性だという。
「彼女は既に家族の一員なので、その意味では(いなくなったら)すごく困りますよ。彼らの多くは、イタリア人がやりたくない仕事を請け負ってくれます。特に高齢者を介護するヘルパーは、ほとんどが外国人。彼らがいなくなったら経済的な問題が出てくるのはもちろん、家から出ることができなくなってしまう人もいるだろうし、イタリアは大変なことになってしまうはず」
ある種深刻なテーマだけに、シリアスな社会派ドラマとして描くこともできたはず。10年の服役を終えた男が過去の自分と向き合うという、長編監督デビュー作“Pater Familias”(02)など、シリアスものを得意としているが、あえて風刺劇にした意図はどこにあるのか?
「まじめで知的な映画としては扱いたくなかった。なぜなら風刺を用いることによって、ドラマチックでシリアスな映画よりも、もっと深い話にすることができるような気がしたからです。もうひとつ言えば、これは移民についての映画ではなく、イタリア人についての映画。彼らがいなかったら、今の自分たちってどうなるのだろうということを問いかけたかった」

突然、移民が消えたことにより、街はにぎわいを失い徐々に混乱をきたす。テレビで移民に対する過激な差別発言を連発するが、実は移民の愛人がいる資産家、移民の子どもを妊娠した元カノがいる刑事、そして、同級生を失った小学生たち。3者がそれぞれにとまどい、焦り、移民がかけがえのない存在であることに気づいていく過程を、シニカルなユーモアを交えて描く。
毒舌資産家のモデルは実在の政治家だそうで、「移民はラクダに乗って帰れ」といったセリフにも出てくる発言は、実際にテレビで聞いた言葉だという。演じたのはイタリアの国民的コメディアンと称されるディエゴ・アバタントゥオーノだ。
「映画は、コメディでおとぎ話の体裁をとっていますが、使われている言葉は現実。重大なことは、話しているのが影響力のある政治家だということ。彼はリビアとの武器の輸出入にかかわった容疑で拘留中ですけれど(笑)。彼は為政者で、被害を受けている人間の振りをして視聴者を笑わせるコミカルなところもあった。だから、聞いている側は笑いたくもなるし、差別主義者だから怒りもわいてくる。そのどっちを受け取ったらいいのか、非常に自分としては微妙なところがあった。ディエゴがすぐにやると言ってくれたので良かった。彼以外にイタリアの俳優であの役をできる人間はいないと思っていたし、断られたら大変なことになっていたよ(笑)」
刑事役のヴァレリオ・マスタンドレアも、現在のイタリア映画界を代表する人気俳優。一方で、子どもたちはオーディションで選び、みずみずしい演技を見せ、それぞれのエピソードが絶妙なハーモニーを奏でている。
「この映画には、物語的な完結はありません。3組の主要人物がそれぞれに完結するという形で終わっています。子どもたちの場合は、最後のトンネルのシーンでうさぎが出てきます。それはかすかな希望があって、未来へのシンボルでもあるのです。また、あの3組は誰をとっても、良いか悪いかと完全には分けられないあいまいな態度をとっているので、そのたびに見ている人間は驚かされるという効果があったと思います」
予定していたロケ地の市長がクランクイン直前に許可を取り下げ、わずか2日で別のロケ地を探さなければならないというアクシデントはあったが、撮影はほぼ順調だったという。だが、イタリアの劇場で予告が上映され始めると、それを見た政治家が憤慨し、議題に取り上げられたたそうだ。
「この映画の話題が連日、新聞に出ていたわけですね。だから、まだ誰も見ていない映画なのに、おかげで有名になりました(笑)。でも、良い面と悪い面がありましたね。政治的で社会派の映画だと思われてしまいかねないので、それは自分としては一番避けたかったことだから。それでも、彼らを怒らせることができたのは自分にとってはすごくうれしかったし、宣伝された資料がたまったのは非常に喜ばしいことでした」
第68回ヴェネチア国際映画祭・イタリア映画ニュー・トレンド部門への出品を経て、母国での公開。観客の反応については、想定通りの好評を得ていると相好を崩す。
「ドラマチックなものを見せると、観客はなんとなく身を守ろうとしますが、コメディならば笑いながら考えさせることができる。実際に、映画を見た人たちから『自分の隣人や、近くにいる外国人たちとの関係をあらためて考えさせられた』と感謝されたんです。コメディにはふたつのタイプがあって、他者を笑うコメディと、自分たち自身を笑うコメディ。この映画は後者なので、だから余計に考えさせることができたのではないかと思います」
移民問題とは縁遠い日本での上映。加えて東日本震災後の来日に関しては、どのような思いだったのか? これには、プロデューサーのフランチェスカ・ディ・ドンナとともに「不安より、日本に来たい気持ちの方が強かった」と声をそろえ締めくくった。
「コンペに選ばれたのは、うれしい驚きでした。いい映画ができたら、いろいろな国で見せたいと思いますから。イタリアでもラクイラで地震があった(2009年)ので、その点については仲間という気持ちがすごくあります。日本の人たちの行動にも感銘を受けましたしね。日本の観客の反応は非常に楽しみです」

左からフランチェスカ・ディ・ドンナさん(エグゼクティブ・プロデューサー)、フランチェスコ・パティエルノ監督
聞き手:鈴木 元(映画ジャーナリスト)
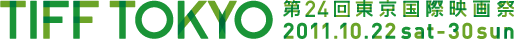

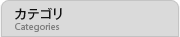

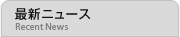




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
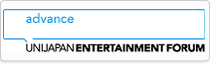

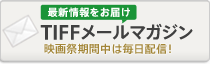
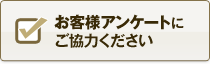

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)