10月27日(木)、WORLD CINEMA『ザ・パワー・オブ・ツー』の上映後、マーク・スモロウィッツ監督、アンドリュー・バーンズプロデューサー、イサベル・ステンツェル・バーンズさん、竹内直実アソシエート・プロデューサー、北岡みさこPRコーディネーターが登壇し、Q&Aが行われました。
日系アメリカ人であるイサベルさんは、日本語と英語で答えてくださいました。

マーク・スモロウィッツ監督(以下、監督):こんばんは。この度は『ザ・パワー・オブ・ツー』を観ていただきありがとうございます。実は今回の上映がインターナショナルプレミアになりまして、それとともにこの作品はある意味、日本とアメリカのラブレターでございます。そして皆様が私どもと同じように感動してくださり、この作品が心の琴線に触れたことを願っています。やはりこの映画祭で上映されたということはこの作品に大きな意味があり、プラスになると思います。そして、今回残念ながら来日は叶いませんでしたが、アナベル・ステンツェルさんのビデオレターをご紹介したいと思います。

【ビデオレターより】
アナベル・ステンツェルさん:カリフォルニアからこんにちは。今回東京国際映画祭に出席できずごめんなさい。『ザ・パワー・オブ・ツー』がこの映画祭に選定されたこと、大変嬉しく思います。東京国際映画祭のスタッフをはじめ、これを実現した皆さんに心から感謝します。
この映画に参加するにあたり、私には多くの夢がありました。それはこの映画が日本の嚢胞性線維症(CF症)患者や移植を待つ患者を支援するということです。日本の臓器移植の現状はアメリカより課題が多いと思います。この映画がこういった課題に直面している日本の患者とご家族の力強さを描いていることを願います。私はこの映画を改正移植法案の実現するために一生懸命努力した皆様に捧げたいと思います。法案改正後の成果はすでに見られ、他の人を助けるために、命の贈り物を提供したドナーファミリーの方々には感謝の言葉がありません。また『ザ・パワー・オブ・ツー』に出演し、勇気と寛大さを持って思いを伝えてくれた皆様に感謝と敬意を捧げます。あなたこそがこの映画のヒーローです。
『ザ・パワー・オブ・ツー』として日本やアジアで臓器提供に対する受け入れを高め、最終的にはドナー登録の数が増え、臓器移植を待つ人が命の贈り物を受けられることを強く願っています。今日この映画を観てくれた皆さんに影響を与え、皆さんが呼吸することの喜びに感謝して欲しいと思います。それこそがわたしにとって映画の最大の成功に繋がります。今日、『ザ・パワー・オブ・ツー』にご来場いただき本当にありがとうございました。
Q:イサさんが映画の中ですごく力強く生きていることに感動しました。イサさんはどうやって今も死の恐怖と戦って生活しているでしょうか。
イサベル・ステンツェル・バーンズ(以下、イサベル):少しだけ日本語で話します。病気の時は、寂しい時も孤独な時もたくさんありました。けれども、わたしは双子ですから、いつもいろんな気持ちをアナと共有し、それはすごく助けになっています。そしてアナだけではなく、主人と多くの周囲の人にいつも自分の感情を表しています。そういう人間の気持ちは恥ずかしいものではないと思っています。そして、わたしの体調が悪く苦痛を感じている時、いつも心がけていたことは、体調はコントロールできないけれども、常にわたしは自分の生きる姿勢や心だけはコントロールできるということです。常に笑顔を忘れないこと、自分が持っていないものや失ってしまったものを数えるのではなく、今自分が手にしていることやものだけを考えるようにしていました。

Q:医療従事者に対する、今後の希望やメッセージがありますでしょうか。
イサベル:たくさん話したいことがありますけど、やっぱりお医者さんたち、患者さんたちみんなにとって一番大切なものは「私は病気だけじゃない、私はほかの趣味とか好きな物とかいろんなパーソナリティもある」。私は慢性的な病気だから、小さい時からずっとこの病気と住んでいます。ですから、私はプロフェッショナルになりました。お医者さんと看護士さんにコラボレーションが大切です。
Q:患者さんとドナーの家族が出会うっていうのは、日本では絶対にできません。アメリカでは、どのようにしてドナーの家族が出会うことが出来るのか、教えてください。
監督:アメリカのシステムですと、まずイサさんのような患者さんが移植コーディネーターにお礼の手紙を書いて、コーディネーターからドナーの家族に「手紙を受け取りますか」と聞くわけです。受け取るか受け取らないか、受け取った後に患者さんに連絡するかしないかはあくまでドナーの家族の意思によるものです。
この映画でご覧いただいたように、ジェームズ(アナの1回目のドナー)の家族とアナの交流というのは本当に素晴らしいものでした。悲しいかな、彼女は拒絶反応が出て、彼の肺を失ってしまいました。彼女はせっかく頂いた肺を失ってしまったということで、ドーン家に対しても罪悪感を持っていた。ただ、この撮影のためにオレゴンにドーン家を訪ねたときに、「彼の肺はなくしてしまったけれども、彼の肺を自分に得られた6年間は本当に素晴らしい贈り物でした」とドーン家の人々に伝えることができたわけです。そして、彼女自身もそれを強く感じることができたわけです。
イサベル:ドナーのご遺族に会うことは、私の人生の一番複雑な気持ちになりました。私のドナーはザビエルという18歳で亡くなった青年で、私は32歳の時に移植を受けました。なぜ若い人が死んで、歳が2倍の自分が生きているのかという不公平は全然理解できない。そして、家族に会った3週間後、私は心も体も頭も全部くたびれて、やっぱり罪悪感が大きかった。彼の家族はあまりお金がないけれど、私たちの家族は旅行できるし、いい学校に行ったので、とってもラッキーだった。ザビエルの死はとても不公平なものでした。
もっともっと日本で移植によって元気になる人が増えたら、もっともっとこういうミーティングとかコミュ ニティーができることを望みます。最初はコミュニティーを作って、そして、人と自分のストーリーを共有すると、だんだん自信を高まる。そして。その自信を 高まった後、移植者は人の前で話すことができる力を持てる。もちろん、自分の病気のことは恥ずかしいものですね。でも、ちょっと練習して、ちょっとコミュニティーをサポートできたら、もっともっと話すことができます。こうやって病気の話すことができるということを日本人の患者さんが見て、移植者たちがもっともっと話してほしいと思っています。
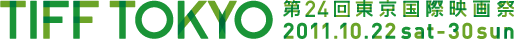

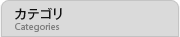

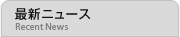




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
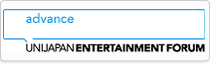

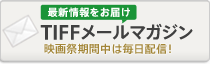
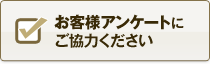

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)