公式インタビュー natural TIFF supported by TOYOTA 『失われた大地』
ミハル・ボガニム監督

人が受ける最も精神的な打撃は、自分の土地から突然引き離されることです
1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故。周辺に暮らしていた人々は、少しずつ明らかになる深刻な事態をどのように知り、避難し、その後どんな思いを抱えて生きたのか。
ミハル・ボガニム監督が念密なリサーチを基に描いた『失われた大地』は、チェルノブイリと同じ「レベル7」を経験し、今後もこの影響と共に生きる日本の観客に強い印象と多くの教訓を与える。同時に本作は「劇に事実の再現はできない。しかし真実を描くことはできる」という古くからのテーゼ通りの、幾つもの寓意を繊細に織り込んだ劇映画だ。この点を中心に監督に語ってもらった。
――チェルノイブリ原発作業者の居住地で、現在は立入制限区域であるウクライナのプリピャチ。この街の人々を描こうと着想したのは?
ミハル・ボガニム監督(以下、ボガニム監督):私はこれまで、東欧に取材したドキュメンタリーを何本か手掛けています。そこでウクライナの人々にとってチェルノブイリがいかに重い存在かを間近に知り、強い関心を持ちました。高レベルの放射性物質が現在も土地を汚染している事実について、ヨーロッパでは多くのドキュメンタリーが作られています。しかし、フィクションのテーマとなることは殆どありません。私は事故の説明ではなく、体験した人々の内面をフィクションで描きたいと思いました。
脚本は、当時プリピャチにいた多くの人々に取材した上で執筆しました。それに私はイスラエル出身で幼い頃にフランスに移住しており、戦争や被災を自ら経験しています。その実感も脚本に描き込んでいます。
――自然豊かな春に起きた悲劇と、10年後の冬の沈黙という対照的な風景。故郷を失った人々の心情をつなげる音楽は、歌謡曲「百万本のバラ」や古いタンゴ。構成と演出にとても正統なドラマづくりを感じました。
ボガニム監督:私は自分の映画の音楽や音に、ただの伴奏ではない記憶装置の機能を与えています。複数の時間と場所をつなげた作品が私には多く、最初の劇映画である『失われた大地』にもその特徴は顕著ですが、やはり音楽にその効果を持たせています。
映画は事故の前夜と当日、避難、10年後と大きく3部からなっています。古典的な劇作の基本である3幕構成に、自然と倣った点はあったかもしれませんね。ただ、私自身は常にドキュメンタリーとフィクションの境界線上で仕事をしてきました。ドキュメントにフィクションの要素を入り込ませた、いわゆる正統とは違うものです。
――〈シネマ・ヴェリテ〉の創始者で知られるドキュメンタリー作家、ジャン・ルーシュに師事されたそうですね。
ボガニム監督:とても素晴らしい人でした。日本では彼の作品を見られる機会は少ないのであれば残念です。彼の手法はヌーヴェル・ヴァーグの作家たちに大きな影響を与えています。私自身も、ドキュメンタリーとフィクションを融和させる手法は彼から学びました。もうひとつは人類学的視点。ルーシュで特に知られているのは、アフリカの宗教的儀礼を記録した一連の作品です。『失われた大地』の、原発関係者遺族の墓参りの場面はルーシュの影響下にあるものです。ウクライナの墓参りは実際このような作法に則るのだと、物語のなかで記録しておきたかったのです。
――では、ロベルト・ロッセリーニの名前をここで挙げても構いませんか?
ボガニム監督:もちろん。現実の人物を基本にフィクションを作ったイタリアン・ネオリアリスモにも、大きな影響を受けています。さらに演出の美学的な面でいうと、『失われた大地』ではロング・ショットにこだわりました。ロング・ショットで俳優にダンスの振付のような動きを求めたのは、テオ・アンゲロプロスやアンドレイ・タルコフスキーを意識しています。結婚式の記念撮影の場面はワンシーンワンカットで、アンゲロプロス的だったでしょう(笑)。リハーサルにとても苦労しました。好きだと言ってくれる人が特に多い場面です。

――タルコフスキーの『サクリファイス』は? 木を植える場面からの連想です。
ボガニム監督:事故前日にリンゴの木を植える父子のシーンの参照にしたのが、まさに『サクリファイス』です。10年後、少年は成長したリンゴの木に語りかける詩を教室で朗読しますね。あれは、プリピャチから避難した実在の少年が書いた詩なのです。そこに『サクリファイス』のイメージを重ねて場面をつくりました。少年は「リンゴの木に名前をつけた」と語ります。どんな名前なのか答えはあるのですが、映画では伏せました。観た人に考えて頂ければ幸いです。
――ヒロインは夫を失った過去と現在、それにふたりの恋人との間で不安定に生きている。この〈引き裂かれた感情〉が映画の主眼でしょうか?
ボガニム監督:大きな災害が起きた時、人々が受ける最も精神的な打撃は、自分の住む場所から去らなければならないことです。人と土地が、突然、引き離されるのです。この感情は映画の重要なテーマです。
――少年の父である原発技師は、守秘義務のため事故の深刻さを口に出せず、せめてもと傘を人々に配る。彼もまた公務と人間性の間で引き裂かれた、象徴的人物でした。
ボガニム監督:当時の原発従事者たちがモデルです。国や政府への忠誠心との間で葛藤し、彼のように狂気に至ったり、自殺したりした技師が何人もいます。知的エリートだった彼らは、実は最も抵抗力が弱かった。科学文明という自分の根拠を突如失い、精神的に崩れてしまったのです。一方でプリピャチに戻っても健康なままでいる森林警備の男性が登場します。彼のように自然の律に従って生きる者には、抵抗力があるのです。この映画が群像劇なのは、同じ土地で同じ体験をしてもその捉え方や影響の残り方、対処の仕方は、その人によって変わってくるのだと表現するためです。
――気になった点を。事故当日、プリピャチ周辺で動物や魚の急に死ぬ姿が、カタストロフィのサインのように描かれています。しかし、今年の日本でナーバスな問題となったのは、動物や魚が内部被ばくしたまま元気に生きていることだったのです。
ボガニム監督:当事者の体験や見聞を描写の参考にしていますが、どうしても証言は過去を「神話化」する傾向を持ちます。日本のみなさんがリアリティという面から疑問を持つのは当然ですが、当時はそれだけの不安がプリピャチの人々を襲いました。目に見えない死の恐怖を示した表現。そう理解して頂きたいと思います。
私からも質問です。他にはどんなシンボルを見つけられますか?
――ヒロインは幸せだった結婚式の時、プリピャチ見学をガイドする10年後と常にマイクを持っていますが、その意味合いは対照的です。それに避難用バスで街を出たヒロインは、10年後もプリピャチ見学バスの車内にいる。彼女の囚われの心情が、未だにバスから降りられない姿によって視覚化されていました。
ボガニム監督:時の経過ということですね。放射能の影響は永く続きます。この映画がプリピャチから周辺の街へ舞台を移すには、放射能の影響の広がりを構造的に表現する意図があります。終盤の道路の汚れた水溜まりもまた、前半の雨との対照でありつつ、放射能は時を経てもまだそこにあると示すものです。
そう、この映画で重要な役割を果たしているのは水や自然です。ヒロインも技師の父子も次第に心を病み、状況に対して抵抗力を失う。ところが無人となった土地では、リンゴの木が大きく育つ。人間のドラマを通して最終的に問いかけたかったのは、人間の知性より自然のほうが賢く、偉大ということなのです。

聞き手:若木康輔(ライター)
失われた大地
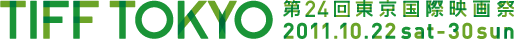

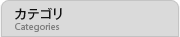

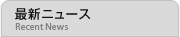




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
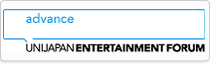

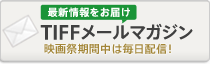
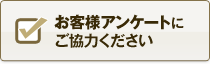

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)