公式インタビュー コンペティション 『羅針盤は死者の手に』
アルトゥーロ・ポンス監督、オスカル・ラミレス・ゴンサレス(プロデューサー)、アンナ・リベラ(衣装)、エドガル・バロソ(音楽)

左からオスカル・ラミレス・ゴンサレス プロデューサー、エドガル・バロソさん、アルトゥーロ・ポンス監督、アンナ・リベラさん
スペインから故郷の現実の生活を見て、マジック・リアリズムがあると気付いた
アルトゥーロ・ポンス監督の『羅針盤は死者の手に』では、国境を越えてメキシコからアメリカに向かおうとする少年の物語が、予想外の方向へと展開していく。少年は奇妙な成り行きで、コンパスを握ったまま死んだ老人と荷馬車で旅をすることになり、そこに様々な人物が乗り込んでくる。堂々巡りに陥る荷馬車はメキシコを象徴しているようにも見える。メキシコ出身でスペインを拠点に活動するアルトゥーロ・ポンス監督、監督夫人で衣装を手がけたアンナ・リベラさん、音楽のエドガル・バロソさん、プロデューサーのオスカル・ラミレス・ゴンサレスさんに話をうかがった。
――ポンス監督は、メキシコからスペインに渡って映画を学び、スペインを拠点にしています。バロソさんはハーバード大学に在籍され、作曲家として受賞歴もあります。ふたりは、以前から“ヴィジュアル・コンポジション”シリーズというコラボレーションを行っていますが、関係は長いのでしょうか。
エドガル・バロソ:18年前に知り合って、一緒にロックバンドをやっていた。アルトゥーロはとてもいいドラマーなんだ。

アルトゥーロ・ポンス監督(以下、ポンス監督):僕がメキシコを離れたあと、バロソがデジタル・アートを学ぶためにバルセロナに来たことがあって、そのときは僕たち夫婦と彼と3人で暮らしていたこともあった。“ヴィジュアル・コンポジション”は今も続いている。僕の映像にバロソが音楽をつけたり、逆に、彼の音楽に映像つけるというかたちで、どちらかというと抽象的で、実験的なこともやっている。

――ゴンサレスさんは以前、『スティグマータ/聖痕』に参加されていました。
オスカル・ラミレス・ゴンサレス:その頃はまだ技術者でした。最初の15年は技術者として関わり、この10年はプロデューサーとして映画を作っています。ポンス監督については、幻想的といっても過言ではないような表現を恐れないところにとても魅力を感じました。映画をエンタテインメントではなく、芸術と捉えているところにも共感できました。2年かけて資金を集め、その間にどういう映画にするかいろいろ話をしました。

――リベラさんは映画以外でも活動されているのでしょうか。
アンナ・リベラ:もともとファッションの勉強をしていたんですが、芝居のことがわかりだしてから、自分が目指しているのはこっちだと気づきました。これまで演劇やテレビで衣装を担当してきて、映画というのははじめてに近かったのですが、自分にとって新しい発見があったので、この分野をもっと開拓していきたいと思っています。

――『羅針盤は死者に手に』では、マジック・リアリズムといいたくなるようなユニークなスタイルが際立っていますが、どのようにこのスタイルにたどり着いたのでしょう。
ポンス監督:スペインに暮らすようになって、ひとつ気づいたことがある。マジック・リアリズムというとラテン・アメリカのものと思われがちだけど、実は世界中に存在していると思う。僕にとっては宮崎駿もモンティ・パイソンもマジック・リアリズムだ。アルゼンチンの作家フリオ・コルタサルが、マジック・リアリズムの作品を書いたのは実はパリにいたときなんだ。僕の場合も、スペインから故郷の現実の生活を見て、そこにマジックがあると気づいたことが大きかったと思う。この映画に登場する人物は僕が作ったキャラクターだと思われているけど、そうでもない。スーパーのカートに石を積んでいる人物は、実際にああいうパフォーマンスをやっている人間だ。お金をとって電気でビリビリさせる子供もそう。マジック・リアリズムは簡単にできる。リアリズムという言葉が物語るように、日々の生活のなかにそのカケラがある。だから、それを集めてモザイクを作ろうとしたのだ。
――映画のあの馬車はメキシコという国の縮図にも見えますが。
ポンス監督:あの馬車にはパラドックスがある。カーナビをつけるわけにいかないのでコンパスにしたけど、方向を指し示すコンパスを持ちながら、みんなどこに行けばいいのかわからない。それは、まさに今の世の中だと思う。インターネットもカーナビもあるけど、逆にコミュニケーションが希薄になって、先が見えなくなっている。映画のなかのひとつの台詞がすべてを物語っている。「自分たちは今どこにいるかわからないし、これからどこに向かうのかもわからない」。
ゴンサレス:カンヌの選定をやっている知人のジャン・クリストフ・ペルジャンに映画を見せたら、こんな話になりました。シンボルがすごくシンプルなので、観客が自由に想像し解釈できる。最近の説明が過剰な映画とは違い、そういうゆとりが残っていると。彼は、メキシコの社会的、政治的な状況を象徴していると解釈していました。あまり政治的にはなりたくないですが、この映画については、まさに今のメキシコの大統領はこうだよねという話になります。砂漠のなかでみんな道を失っていて、しかもどんどん腐敗していく死者に導かれているというのがまたおかしいと思います。
――バロソさんは、時間とか空間をテーマにした曲を作っていますが、この映画の時空についてはどんなことを意識して、音楽を作ったのでしょうか。
バロソ:監督からはバイオリンを絶対に入れたいという要望があった。僕たちは昔からの友だちなので、ひと言だけで何を考えているかお互いにすぐわかってしまう。そんな関係がいい影響を及ぼしたと思う。音楽の位置づけについては、映画と別のものと捉えるのではなく、音楽も登場人物として馬車に乗っているという考え方で曲を作った。だから、音楽に独自の感情を持たせることが重要だった。ただ、けっこう悪戯もやっている。よく聴いてないとわからないような微妙なものだけど。
――この映画には奇妙な人物がいろいろ登場してきますが、リベラさんはどのように衣装を決めたのでしょう。
リベラ:まずふたつのことを下調べする必要がありました。ひとつは映画に関する勉強です。もうひとつはメキシコについて知ることです。メキシコはもう何度も行っていますが、スペインと全然違うので驚きがあります。この映画では、撮影の3か月前にメキシコに行き、メキシコ人のアシスタントをつけてもらって、街を行き交う人たちを観察して決めていきました。なので、スペインで自分が考えていたアイデアとは変わりました。
――この映画では、腐敗していく死者、葬式の泣き女、廃墟になっている教会、壊れた時計、衰退していくイメージが際立ち、それらが、ある種ブラックユーモアになっていると思います。
ポンス監督:その衰退を代表しているのが映像そのものだと思う。最初のシーンでは、子供が遊んでいて色がたくさんあり、そこから30分くらいはリアルな世界になっているけど、徐々に幻想的な世界に入っていく。色が褪せていき、夜がこないというように時間の感覚も失われ、ロジックも消えていく。この映画の最初と最後では、映像の彩度が60%くらいに落ちている。
バロソ:今のメキシコには暴力やドラッグがはびこっていて、問題が山積している。この映画はそれを網羅している。ただ、問題をそのまま描くのではなく、ブラックユーモアで表現しているところが魅力だと思う。
ポンス監督:メキシコには同世代の素晴らしい監督たちがいるけど、自分がメキシコに住んでいないので彼らとは交流がない。僕は、メキシコのことでも他のことでも、みんながやっているのとは違う個人的な観点で語ることが大事だと思う。それは人に対して敬意を払うことでもある。政治家というのは、みんなに同じことを同じかたちで語る。それはやってはいけないことだ。僕は自分なりの芸術的なかたち、サーカスティックで、シュールレアリスティックなスタイルで表現したい。
アルトゥーロ・ポンス監督にとっては、スペインを拠点に活動することが重要な意味を持っている。離れた場所からメキシコを見つめることが、インスピレーションの源となり、現実をまったく違ったかたちでとらえる独自の映像表現を切り拓いているからだ。
聞き手:大場正明(映画評論家)
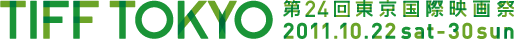

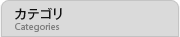

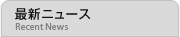




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
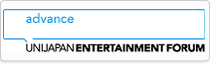

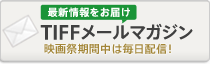
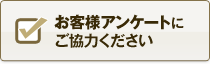

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)