10/28(金)コンペティション部門 『羅針盤は死者の手に』のQ&Aが行われ、アルトゥーロ・ポンス監督、プロデューサーのオスカル・ラミレス・ゴンサレスさん、衣装を担当したアンナ・リベラさん、音楽を担当したエドガル・バロソさんが登壇しました。

オスカル・ラミレス・ゴンサレスさん:私たちの作品をご覧いただいてありがとうございます。そして東京国際映画祭に作品を持って来れたことを非常に嬉しく思っています。この作品は金銭的にあまり恵まれず、関わった人々の無償の愛により完成しました。私は日本の文化が大好きで、ずっと日本に来たいと思っていました。初めて日本に来てみて、全てのことが想像以上に素晴らしく、驚くことばかりです。日本の皆さん、東京のみなさんは、とても素晴らしいと思います。ありがとうございます。

アルトゥーロ・ポンス監督(以下:ポンス監督):(日本語で)いらっしゃいませ!
今、自分の言葉を、スペイン語を使って話したくないと思っています。スペイン語を使うことで、言葉を汚してしまうのではないかと感じています。前もって書いてきたものがあリますので、これを日本語と英語だけで伝えてもらいたいと思います。

通訳:何故この作品を製作したかというと、魂のある作品を作りたかったからです。その魂は喜びのあるものです。もしかしたら上手く伝わってないかもしれませんが、この2時間で私たちの魂が皆さんに伝わったことに関して、とても責任を感じています。2時間の間、私たちを信じ、身を委ねてくださったことを非常に感謝しております。作品を通じて、達成したいと思っていたこと、願っていたことが叶っていることを祈ります。
アンナ・リベラさん:本日は、お越しいただいて本当にありがとうございました。映画が好きでこの作品を作った私たちが、映画を作っている時と同じくらい東京国際映画祭を楽しんでいます。この映画を見て、皆さんが楽しんでいただけたことを願っております。

エドガル・バロソさん:本当に日本に来ることができて嬉しく思っています。ここ数日、日本で過ごしていて、色んなことを楽んでいます。日本語でまっ先に知りたいと思ったのが「(日本語で)日本大好き!」という言葉です。この言葉を伝えたくなるくらい東京での時間を楽しんでいます。日本の皆さんがお互いに非常に敬意を払っていること、とても親切であることに感激しています。この2時間、私たちの映画を見ていただいて、本当にありがたいと思っています。私は日本から学ぶことが沢山あると思っていますし、今回日本に来ることができたことが、私たちにとってのギフトだと思っています。

ポンス監督:(日本語で)みんな綺麗です!
ポンス監督の一言で、会場は和やかな雰囲気になりました。

Q:羅針盤を持ったパシアノを演じたペドロ・ガメスさんは、実際にお亡くなりになられたということですが、荷馬車に乗っているシーンは亡くなられてから撮影したものでしょうか?
ポンス監督:ペドロ・ガメスさんが亡くなったのは撮影が終わった後です。彼は素晴らしい俳優さんだったので、本当に死んでる様に見えたのかもしれないです。実は彼は撮影中に眠ってしまうことが多かったんです。長いシーンでは彼が眠ったまま撮影をしていて、死んだはずの彼が起きてしまったことで撮り直しになることがありました。よく見ていただくと分かるんですが、シーンによっては動いてしまっているところがあります。彼は5週間同じ姿勢で撮影をしてたので、馬車に乗るとすぐにポーズを作っていました。高齢で耳が遠かったので、彼が動いてしまうとチェンチョ役のガエルが「今撮影してるから動いちゃ駄目ですよ。」と伝えたりすることがありました。
Q:ユニークな作品をありがとうございました。全編屋外での撮影で、かなり過酷だったのではないかと思います。その中で、長回しや、360度カメラが回るシーンがあったり、凝った映像が沢山ありました。夕日が沈んでいくシーンは恐らく自然条件が整うのをじっと待って撮影されたと思います。最近ではCGを使用して比較的簡単に映像が作ることができると思いますが、このようなシーンにこだわった意図、苦労した点を教えてください。
ポンス監督:色んなシーンにトリックを使っています。これこそ映画のマジックだと思っています。夕日のシーンについては、確かに独特なものだと思います。撮影の1日前に、撮影担当と話し合いをしたのですが、実際撮影を行なってみると、誰も理解してくれていませんでした。私はこのシーンには魂が込められていると思っています。ヨガをした時などの最後に、深呼吸をしてリラックスをするような役割を果たしていると思います。アニメーションを使うこともありますが、最初にお話したように、魂のある作品を作りたかったので、今回はCGを使いませんでした。
Q:とても不思議な映画、というのが率直な感想です。夕日のシーンで気がついたのですが、旅を描いた映画だと夜のシーンが使われることが多いと思いますが、この作品には夜のシーンが全くありませんでした。まるで長い長い一日を見ているような、何日間にも及んでいるような不思議な錯覚に捕らわれたんですが、監督はこの2時間を一日として捕らえていたのでしょうか?
ポンス監督:この作品では、空間に対して特別な試みをしています。空間のロジックを壊すと同時に、時間のロジックも壊したいと思いました。空間と時間のロジックを失うと、自分を見失い、どこにいるか分からなくなる感覚が強くなります。夕日が沈むシーンは、おっしゃる通り時間の感覚がないので、それが一日なのか数日なのかは定められていません。私はロジックなものを見せることは映画的ではないと考えていて、できるだけそういうものを排除して、映画らしさを出したかったのです。
オスカル・ラミレス・ゴンサレスさん:素晴らしい観察をしていただいてありがとうございます。
監督の言葉に付け加えますと、映画を見るということは方向性が見えなくなることだと思います。この作品を見ると一日なのか、三週間なのか、三ヶ月なのかわからなくなってしまう。政治やドラッグ、暴力や移民、教育等の問題について触れていますが、その全ての方向が見えなくなってしまいます。そういう感覚になって欲しかったんです。それがこの作品の目的でした。それを達成するために様々なディテールを詰め込みました。何かが起きるとまた次の瞬間に何かが起きるというような構成になっているので、私たちの予想通りに見ていただけて嬉しく思っています。よく観察していただきました。
ポンス監督:(日本語で)いいねぇ!
私の解釈を言わせてください。最初に脚本を読んだ時に、この作品はリアリティについての映画ではなく、フィーリングや感覚の映画だと思いました。
魂のロードムービーだと思っています。
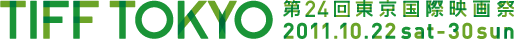

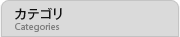

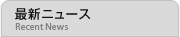




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
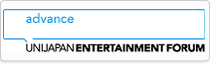

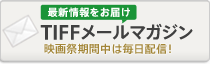
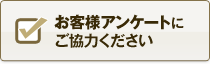

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)