公式インタビュー 日本映画・ある視点 『レッド・ティアーズ~紅涙~』
辻本貴則監督、倉田保昭さん

日本の映画、特にホラー映画の英語タイトルは総じて曖昧なものが多いなか、”Monster Killer”(モンスター・キラー)は、やや一般的だが潔くて分かりやすいタイトルに思える。しかしながら、これは今年の東京国際映画祭で上映されたアクション・ホラー映画『レッド・ティアーズ~紅涙~』の正式な英語タイトルではない。
「映画祭に間に合わせるため、急いで英語タイトルを考えなければいけなかったのです」と、プロデューサー兼出演者の倉田保昭は振り返る。日本語のタイトルを翻訳すると”Red Tears”になるが、倉田は海外配給を見据えて、誤解を避けるため、”Sword of Blood”というタイトルにすることにしたという。
倉田はアジアでその名声を確立しているアクションスターである。なかでも1970年代後半、彼がキャリアをスタートさせた香港での評価が高い。彼は自身のプロダクション会社で『レッド・ティアーズ~紅涙~』の企画を練り上げ、映画化させた。
「当初から女性を主人公にしたアクション映画を作りたいと思っていました。そこにもう少し何か欲しいと考えて思いついたのがヴァンパイアでした」。
映画の中の“モンスター”は厳密にはヴァンパイアではない。『レッド・ティアーズ~紅涙~』は猟奇的連続殺人を扱う映画として、おびえた若者が暗いトンネルで見知らぬ者に襲撃されるシーンから始まる。本作の独創的なタッチで描かれるある場面で、被害者がまだ息のあるうちに文字通り折り曲げられ、スーツケースに詰め込まれる。影しか見えない殺人者は、じめじめした薄汚い地下牢にそのスーツケースを運びこみ、その場にぴったりな芝居がかった大仰な方法で斬首する。
本作は倉田にとって初めてのホラー映画であるため、監督を辻本貴則に依頼した。しかし、辻本監督は“ホラー映画監督”というレッテルには異議を唱える。自身のジャンルは“バイオレンス映画”だという。
「バイオレンス映画にはまずストーリーがあり、そのなかで暴力的なシーンを作りますが、ホラー映画はもっと恣意的です。初めにホラーの要素ありきで、そこからストーリーを組み立てるのです」。
明らかに今回のケースでは、倉田が望むもの――ヴァンパイア、女性の主人公、アクション――を辻本監督に伝え、それらをふまえたストーリーを作るよう求めた。
脚本の米川榮一は東京都下の刑事ふたりの姿を描いた。ひとりは若く理想に燃えた刑事(石垣佑麿)、もうひとりは皮肉っぽい一匹狼タイプのベテラン刑事(倉田)。彼らは連続殺人犯を追っている。この設定のなかで、辻本監督はこれ以上ないほど存分に血糊を使い、自分らしさを表現した。「私が倉田さんをこの方向に引っ張りました。それが正しかったのかどうかは分かりません。やりすぎだという声もあるかもしれませんね」。
若手刑事・鉄雄はベテラン刑事・三島が犯人だと疑っている女に惹かれていき、ふたりの対比が際立つ。鉄雄は通常の方法で殺人犯を捕らえようとする一方、三島は猟奇的殺人犯と長年闘ってきた結果、自分自身も残忍な資質を帯びるようになっていた。
「彼はヒーローではありません。彼は復讐心に燃え、こういったモンスターと闘うには自分自身が悪にならなければならないと分かっているのです」。倉田は自分の役について語る。
では鉄雄はヒーローなのか?
「難しい質問ですね」と辻本監督は言う。確かにこの古典的な善悪対決の作品世界では、鉄雄はちょっと優しくセンチメンタルすぎる。
「私が鉄雄を演じる俳優に言ったのは、鉄雄はあまり好かれるタイプではない、ということです。昔なら彼はヒーローとは呼ばれなかったでしょう。重要なのは三島との対比です。それがストーリーを牽引しているのです」。

それでもやはり、この映画はアクションシーンを中心に作られており、ワイヤーアクションを含めてそのほとんどすべてを倉田が演じている。香港映画の影響について倉田は語る。
「香港映画はオーバーアクションでやり過ぎ。一方、日本のアクションは地味なことが多く、同じようには観客を満足させられない。私は香港スタイルの方が好きですが、香港では『チャイニーズ・ゴースト・ストーリー』(87)までワイヤーは使っていませんでした。私のチームは9年前に『黄龍 イエロードラゴン』で初めて日本映画にワイヤーアクションを取り入れました」。
いずれにせよ、この映画の特殊効果の説明としてぴったりな言葉は“アナログ”である。いわゆる“かぶりもの”映画の影響を受けている。1960年代後半から70年代にかけて日本のテレビで人気を博した、マスクをかぶったSFスーパーヒーローの一連の作品を指す“かぶりもの”だが、辻本監督を含め現代の若手監督はまさにそれを見て育った世代である。
倉田はそういった辻本のカラーについて、全く違和感はなかったという。さらにどのような映画にするかは、個人の芸術的なこだわりよりも予算上の制約に大きく左右されるという。
「正直に言えば、十分に予算があるなら、フルCGで映画を作りたいですよ。しかし私はアクション俳優ですので、地に足がついています。武術はこの作品の重要な部分でありアナログであるべきだと、我々ふたりとも考えています。でもハリウッドスタイルでできたらすごかっただろうね」。

聞き手:フィリップ・ブレイザー(映画ライター)
レッド・ティアーズ~紅涙~
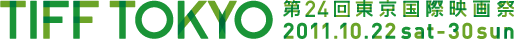

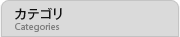

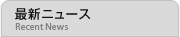




 Check
Check




![みなと上映会 2011年10月29日(土)六本木ヒルズアリーナ[TIFF park] 入場無料 申込み不要 ※小雨決行・荒天中止](/ja/home/ban/jpg/bnr_minato.jpg)
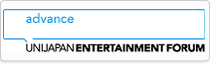

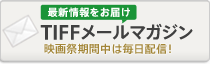
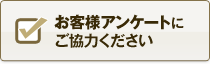

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)